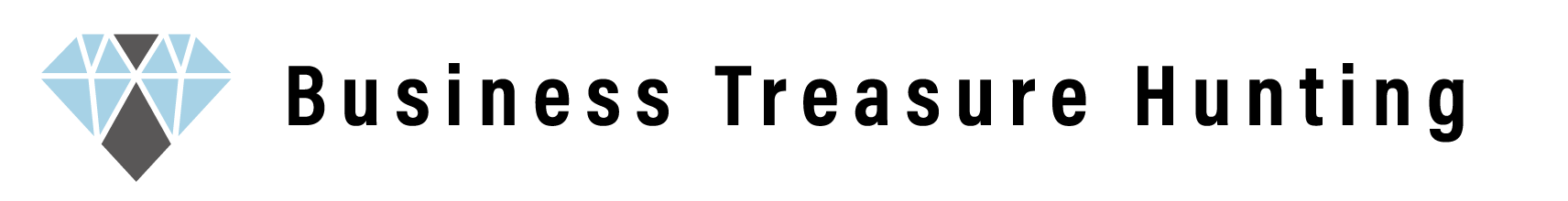知的財産権の中でも、特許と比較して語られることの多い実用新案。費用や審査におけるハードルが低いことから、「まずは実用新案登録をして、商品の売れ行き次第で特許出願に切り替えよう」と考える人も多くいます。本記事ではそんな実用新案について、絶対に押さえておきたい基本知識をまとめました。
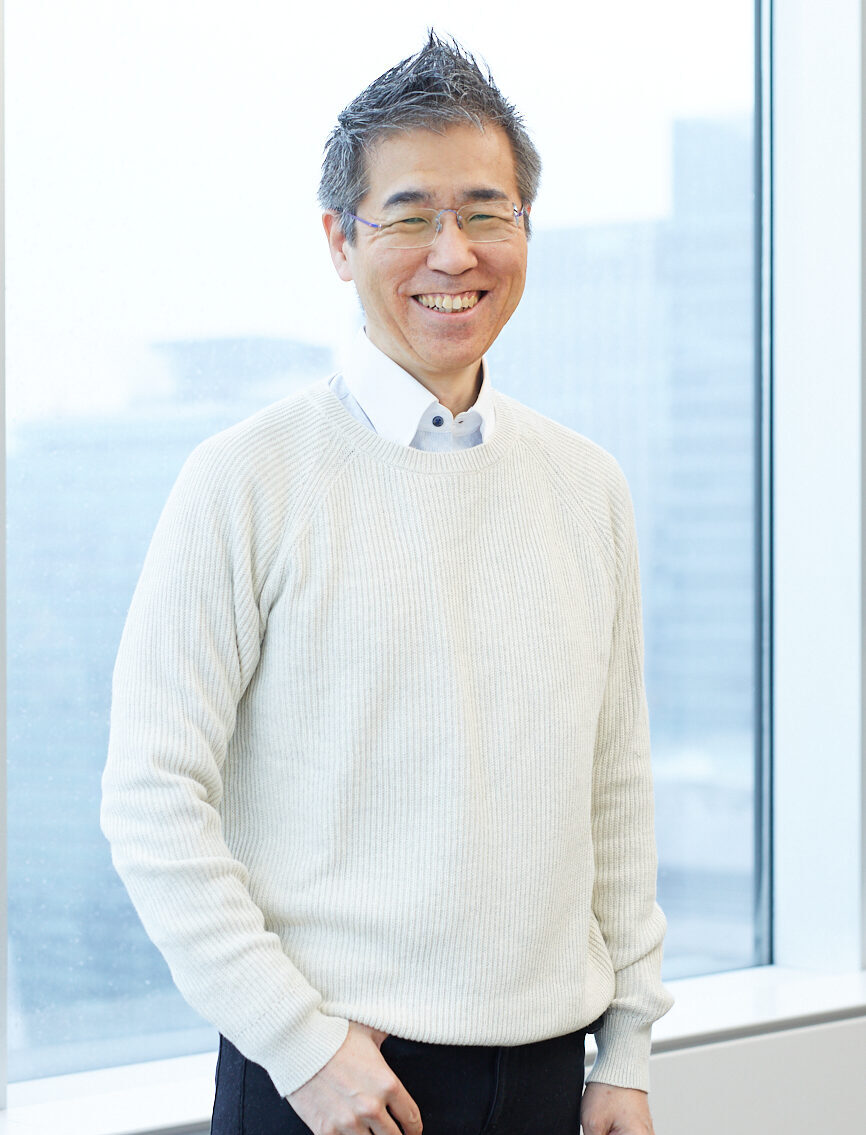 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。1.実用新案とは?
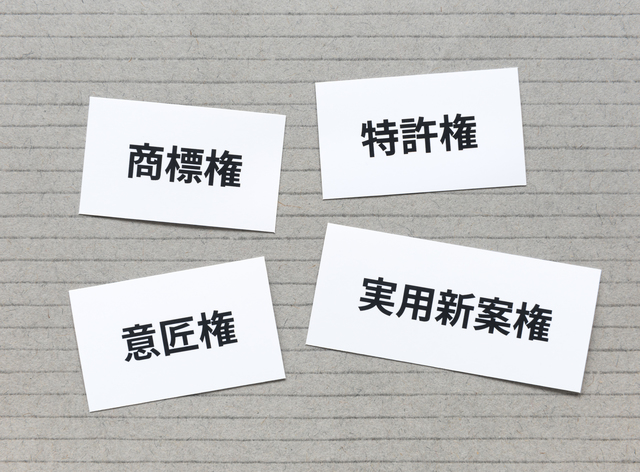
実用新案には、革新的で壮大な発明というよりも「人々の生活を豊かにするためのちょっとしたアイデア」が多く登録されています。出願から権利取得までの期間が短く済み、費用も安価に抑えられることも特徴です。
出願のハードルが低いだけにメリットだけでなくデメリットも目立つため、権利取得には慎重な判断が必要とされます。
1-2.特許との違いは?
特許と実用新案では権利の存続期間も異なります。特許では権利が出願から最大20年保護されるのに対し、実用新案は最大で10年です。
実用新案は特許と比べると権利の範囲が限定されています。特許は製品の製造方法そのものや、コンピュータプログラムなど、広範囲の高度な技術が出願の対象となります。一方、実用新案は物品の形状や構造、あるいは組み合わせに関する技術が対象となっています。
また、1.でも触れた通り実用新案は特許と比べて出願から権利取得までの期間や費用を短く安く抑えることができます。その理由は前述の通り、実用新案には高度な技術が求められないからでもあります。
審査では書類の記入不備がないか、実用新案の要件を満たしているか、といった形式的な内容が書類ベースで判断されます。そのため審査期間そのものが短く、出願書類の補正指令が通知されなければ2ヶ月程度で権利を取得することも可能です。
さらに特許では、審査において「新規性」「進歩性」などの要件を満たしているか否かを確認する「実体審査」が行なわれます。
その審査にクリアした出願だけが特許として登録されるため、他者からアイデアを模倣された際にはすぐに権利を行使して模倣行為の中止を命じることができます。
しかしながら実用新案では審査が形式的な内容をチェックするだけに留まるため、すぐに権利を行使することはできません。
権利者本人であってもも、実用新案の権利を行使するためには特許庁に技術評価を請求し、権利の有効性が評価書において認められなければ模倣を中止させることもできないのです。
2.身近な事例
誰もが知っている有名な製品の中にも、実用新案登録をされたヒット商品が潜んでいます。たとえば、朱肉がなくてもインクの滲みなどなくきれいに捺印ができるシャチハタの『Xスタンパー』。

引用元:https://www.shachihata.co.jp/xstamper/index.php
この商品の実用新案登録はすでに権利期間が満了していますが、朱肉を必要としないハンコといえばほとんどの人々がシャチハタを真っ先に思い浮かべるのではないでしょうか。
あるいは、今も多くの商店やメーカーで販売されているカレーパン。諸説あるものの、1927年に『名花堂(現カトレア)』が実用新案登録を行なった『洋食パン』が起源とされています。
カトレア の 元祖カレーパン!!!
元祖という言葉に納得。
普通なのに普通じゃない!!カレーがパンに合う最高な濃厚さ…ご飯が食べたくなるカレーとは違う…さー散歩🚶#名花堂 #カレーパン pic.twitter.com/nqqbR6YBml
— sayaka (@snrs38) November 4, 2017
そして、現代ではフローリングの床を掃除する際に欠かせない存在となった花王の『クイックルワイパー』。

引用:https://www.kao.com/jp/products/quickle/4901301262790/
こちらも権利期間がすでに満了しており類似製品が市場に多く出回っていますが、この形状のフローリング清掃用品の名称といえば真っ先に『クイックルワイパー』を想起する人が大多数でしょう。
このように、私たちの身近なところに実用新案は根づいています。
3.実用新案権を取得するまでの流れ
実用新案権は、特許などの他の知的財産権と比べて出願から権利取得までが比較的容易とされています。その理由は、主に審査内容が簡易であるためです。
下記の記事では、実用新案の出願においてどのような手続きが必要であり、どのような審査を経て登録されるのかについてまとめています。事前準備からアイデアが実用新案登録されるまで、具体的な流れをあらかじめ把握しておきましょう。
4.実用新案権の取得にかかる費用
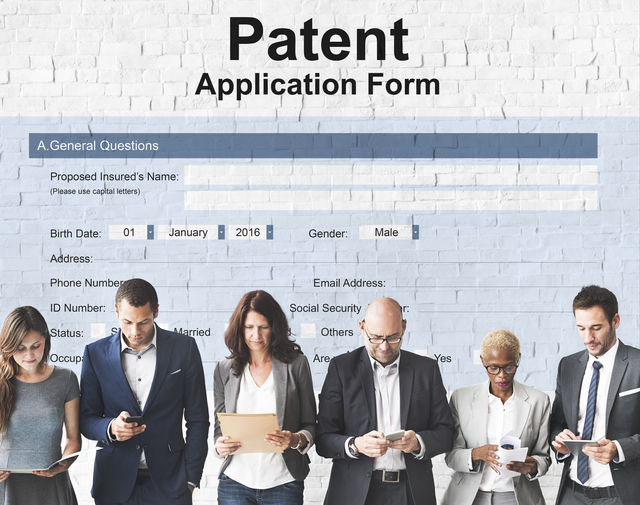
実用新案権は、特許などの他の知的財産権と比べて比較的安価な費用で取得することができます。3.で解説したように、実用新案は審査内容が簡易なものであることから特許事務所などに依頼した場合でも費用を安く抑えることができます。
下記の記事では、そんな実用新案権について出願から取得までに必ず発生する費用や、権利の有効性を確認する際に必要となる費用などについてまとめました。
実用新案では登録料を納付するタイミングが特許などとは異なるため、事前に把握しておくと安心です。さらに、記事内では特許事務所に依頼した場合の代行費用の相場についても工程ごとにまとめています。
特許庁へ支払う手数料の具体的な金額が把握できると共に、特許事務所へ代行依頼をするメリットについても解説していますので、検討材料としてお役立てください。
5.実用新案のメリット・デメリット
知的財産権の中でも、実用新案権は取得におけるメリットとデメリットとがわかりやすい権利といえます。また、実用新案権と並んで比較されることの多い特許権とは切っても切り離せない関係があり、メリットにもデメリットにも特許が深く関わっています。
下記の記事では、そんな実用新案権の取得における代表的なメリットとデメリットについてまとめました。「とりあえず取得してみよう」と行動に移す前に、本当にそのアイデアが実用新案に適しているのかを判断するための一助となれば幸いです。
6.実用新案の出願における注意点

実用新案には、出願時や権利取得後において気をつけなければならないポイントが存在します。たとえば、権利の存続期間やそれに付随する権利の更新、出願内容の公開時期、他者に模倣された場合や権利の無効を申し立てられた際の対応など、事前に把握しておくことで実用新案に対する理解をより深められるはずです。
下記の記事では実用新案に関する6つの注意点についてまとめています。5.のメリット・デメリットと併せて注意点をしっかりと把握しておきましょう。
まとめ
特許よりも容易に権利取得ができ、他者からの模倣行為などに対して抑止力を発揮することのできる実用新案。権利取得までの流れや費用、メリット・デメリットから注意点まで理解を深めれば、きっと万全の状態で出願に臨めるでしょう。