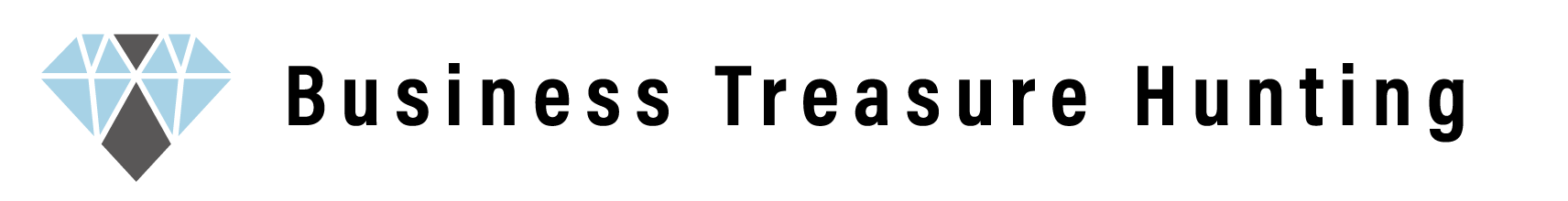特許と並んで語られることの多い実用新案。なんらかのアイデアを権利化したいと考える際、どちらがより適しているのだろうと悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。この記事では実用新案の概要を述べるとともに、特許と比較してどのようなメリット・デメリットがあるのかについて解説します。
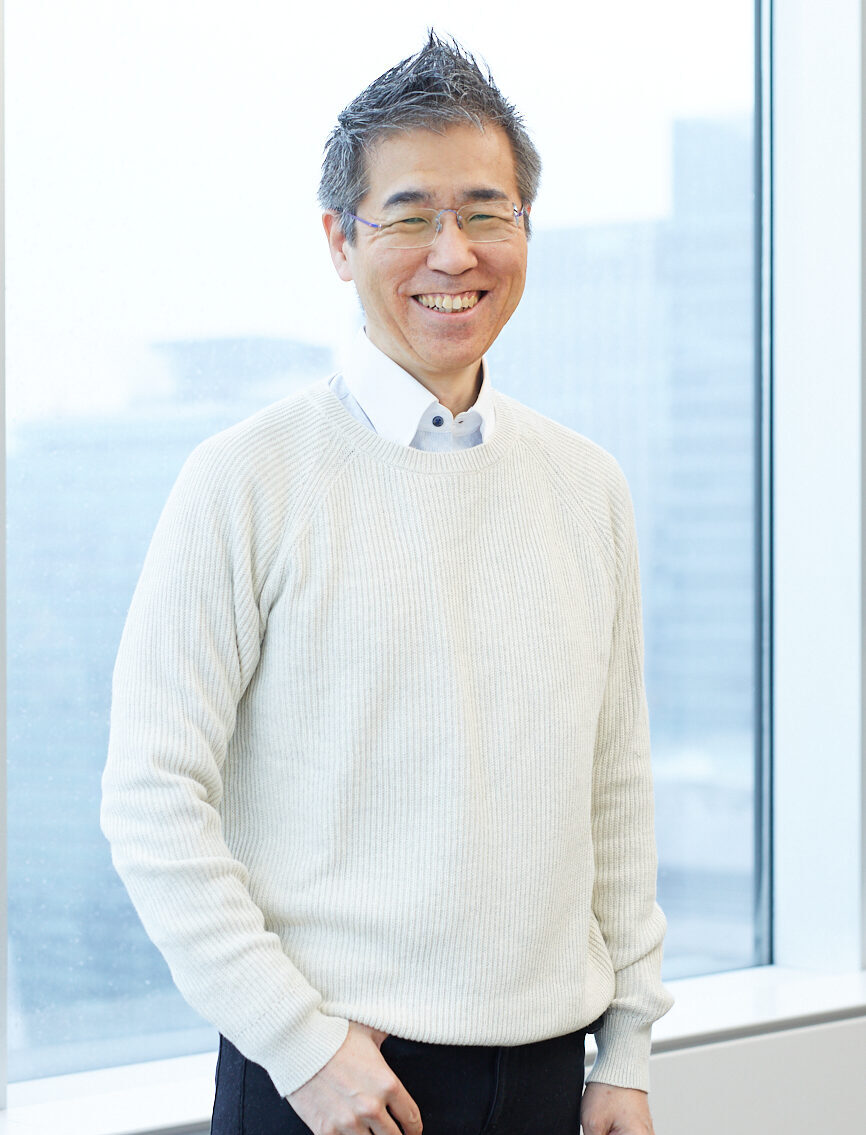 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。実用新案とは?
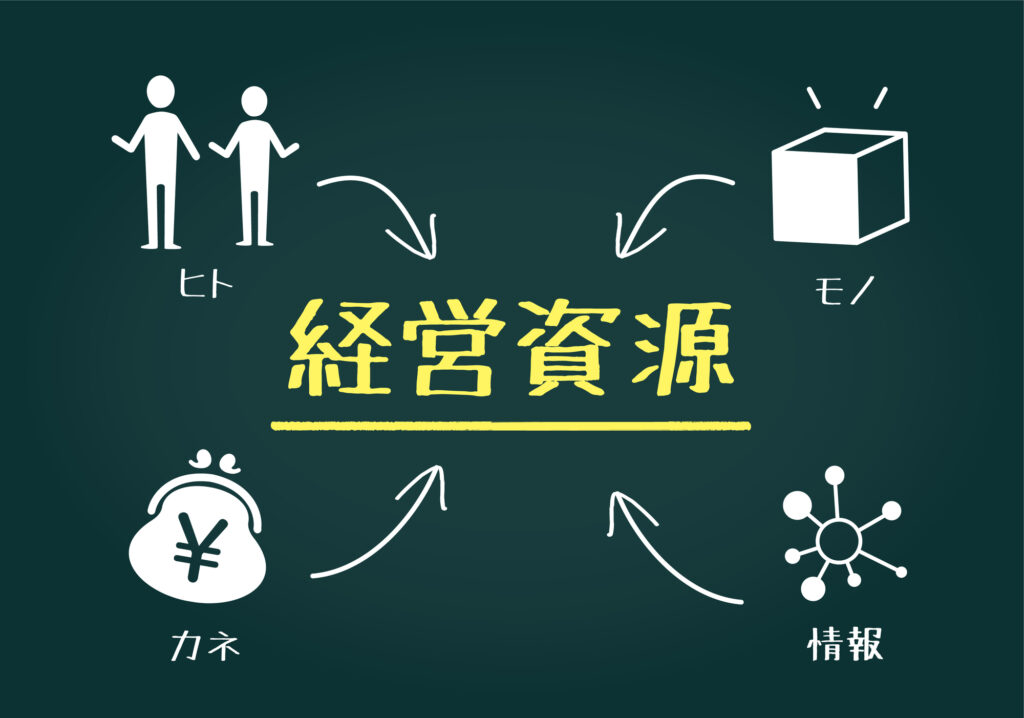
実用新案とは、物品の形状や構造、あるいは組み合わせに関する技術のことを言います。特許とは異なり、コンピュータプログラム自体や、製品の製造方法そのものなどは権利の範囲に含まれません。
革新的で壮大な発明というよりも、「人々の生活を豊かにするためのちょっとしたアイデア」というふうに考えるとイメージが湧きやすくなるでしょう。
実用新案権を取得するまでの流れ
実用新案権は、大きく分けて「出願」「審査」「登録」の3つのステップで取得できます。
まず、出願書類にアイデアの詳細を書いて出願(申請)します。次に、書類の記入方法や内容に不備がないかの審査が行なわれます。最後に、審査を通過すれば登録料を支払い、正式にアイデアが実用新案として登録されるという流れです。
実用新案権の取得にかかる費用
実用新案権の出願から取得までにかかる費用には、出願の際に支払う出願料と審査を通過した際に支払う登録料があります。
| 費用 | |
|---|---|
| 出願料 | 14,000円 |
| 登録料 | 2,100円+請求項の数×100円 |
出願料は14,000円。登録料は2,100円+請求項の数×100円です。登録時には3年分の登録料を支払う必要があるため、計算式は(2,100円+請求項の数×100円)×3となります。一般的に、3年分の登録料でも1万円を超えることは少ないでしょう。
特許と比較した実用新案のメリット

特許と比較して実用新案にはどのようなメリットがあるのかについて解説します。
短期間で権利を保護できる
特許と比較して、実用新案は出願後に審査が迅速に行なわれます。結果が出るのも早いため、短期間でアイデアの権利を保護できるというメリットがあります。
実用新案の審査では、書類の記入方法や出願内容に不備がないかといった形式のみが重視されています。そのため出願から審査、権利の取得まで、不備がなければ2〜3ヶ月程度で実用新案権を取得することも可能です。
一方で、特許には出願から取得まで複数の工程を踏まなければなりません。
まず特許を出願すると、実用新案と同じく記入方法や出願内容に不備がないかといった確認を指す「方式審査」が行なわれます。
「方式審査」を通過すると、出願者が自発的に「出願審査請求」を行なうことで「実体審査」が行なわれます。この審査では、実用新案にはない詳細な確認が行なわれます。出願した発明が「新規性」や「進歩性」を満たしているのか、その発明に実現性はあるのか、といった特許要件の有無を審査されるのです。
この「実体審査」ですが、審査結果が通知されるまでに2020年度では平均で10.2ヶ月ほどの期間がかかるとされています。さらに「実体審査」を通過できず拒絶理由通知が届くと、意見書や補正書を提出して再び審査を受ける必要があります。
この場合、平均の審査待ち期間10.2ヶ月に加えて数ヶ月〜1年以上の期間がさらにかかります。そのため、出願から特許権取得までにかかる実際の期間は短くても1年弱、長ければ数年かかることもあるのです。
費用が安く済む
実用新案は、特許と比較して安価な費用で権利を取得することができます。限られた予算で権利を保護できるため、安価で同業他社の模倣を抑制できるというメリットがあります。
実用新案にかかる費用は、出願料14,000円と、登録料(2,100円+請求項の数×100円)×3年分。多くの場合、トータルで3万円未満に費用を抑えることができます。
一方、特許では出願料と登録料以外に、出願審査請求でも費用が発生します。
| 費用 | |
|---|---|
| 出願料 | 14,000円 |
| 出願審査請求料 | 138,000円+請求項の数×4,000円 |
| 登録料 | 2,100円+請求項の数×200円
※登録が認められた初年度は3年分の登録料納付が必要 |
順を追って解説すると、特許の出願料は実用新案と同じ14,000円。次に出願審査請求にかかる費用は特許印紙代138,000円+請求項の数×4,000円。最後に登録料は実用新案と同じく(2,100円+請求項の数×100円)×3年分です。
出願審査請求において発生する費用が大きいため、出願から登録まで一般的に3万円未満で抑えられる実用新案と比べて10万円以上の費用が必要となります。
また、上記は自力ですべての手続きを行なった際に発生する最低限の費用です。弁理士などの専門家に依頼した場合、調査費用や書類作成費用、特許の実体審査において拒絶理由通知を受けた際の対策費用などが別途発生します。
特許出願に変更できる
実用新案は、出願日から3年以内であれば特許出願に変更できます。このルールを活かして事業拡大に役立てることも可能です。
たとえば、Aさんの会社でヒットが見込めるかどうかわからない製品が開発されました。販売開始時期が迫っており、特許権を取得するには時間もお金もありません。
そこで、短期間で安価に他社からの模倣を防ぐ手段として実用新案権を取得することにしました。今後、製品の販売数が順調に伸びるようであれば特許出願に変更する予定です。特許権が取得できれば、製品に関するアイデアを長期間、より安定して保護できる体制を整えるようになります。
特許と比較した実用新案のデメリット

特許と比較して実用新案にはどのようなデメリットがあるのかについて解説します。
信頼性が低い
実用新案は簡易かつ迅速な形式だけの審査が行なわれます。形式さえ不備がなければ実用新案として登録されますが、そのアイデアの権利が有効であるか否かの評価がなされることはありません。
そのため、もしも他社にアイデアを模倣されてもすぐに自社の権利を主張することはできません。まずは実用新案の権利の有効性について特許庁に「実用新案技術評価書」を請求し、評価結果に問題がなければようやく他社に対してアイデアの使用の中止を求めることができるようになるのです。
評価書において権利の有効性が認められなければ、中止を求めることもできません。
一方で、特許は形式的な審査だけでなく「実体審査」において、「新規性」「進歩性」などの特許要件が厳しく審査されます。その審査に通過したアイデアだけが特許を認められます。そのため、アイデアを他社に模倣された際はすぐに権利を主張し、アイデアの使用の中止を求めることが可能です。
保護期間が短い
実用新案の権利の保護期間は出願日から最大10年、特許の保護期間は出願日から最大20年です。スピーディーに権利を保護できる一方で、保護期間そのものが短いというデメリットがあります。
実用新案の登録事例

それでは最後に実用新案登録された製品の事例を紹介します。
シャチハタ『Xスタンパー』
スタンプ台や朱肉のいらないハンコとして、オフィスや家庭で広く愛用されているシャチハタ株式会社の『Xスタンパー』。特殊な構造のプラスチック材でできた印自体にインキが含まれており、滲んだり垂れ落ちたりもせずきれいな捺印ができる大ヒット商品です。
この商品の実用新案権の保護期間は1984年に満了しています。しかしながら、同社の「特許権だけでなく、実用新案、意匠権、商標権で“多重防護”する」という知財戦略が功を奏し、業界内で「シャチハタの製品は模倣がしにくい」という認識が浸透していったと言えます。
まとめ
迅速・安価に権利を保護できるというメリットを持つ実用新案。審査が簡易であり、特許と比較して出願しやすい知的財産権であると言えます。「ライバル企業に真似されたくないけど、時間もお金もかけられない」というケースにおいて、まずは実用新案権の取得を検討してみてはいかがでしょうか。