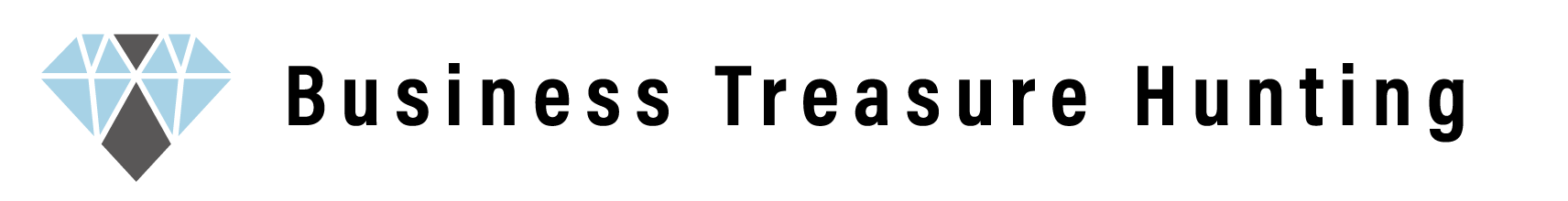私たちの日常生活を便利にする「ちょっとした発明」を中心にさまざまなアイデアが登録されている実用新案。知的財産権の中でも、特許と比較して短期間で比較的容易に登録できるものであるといえるでしょう。本記事では実用新案における具体的な出願方法や権利の有効性の確認方法について解説していきます。
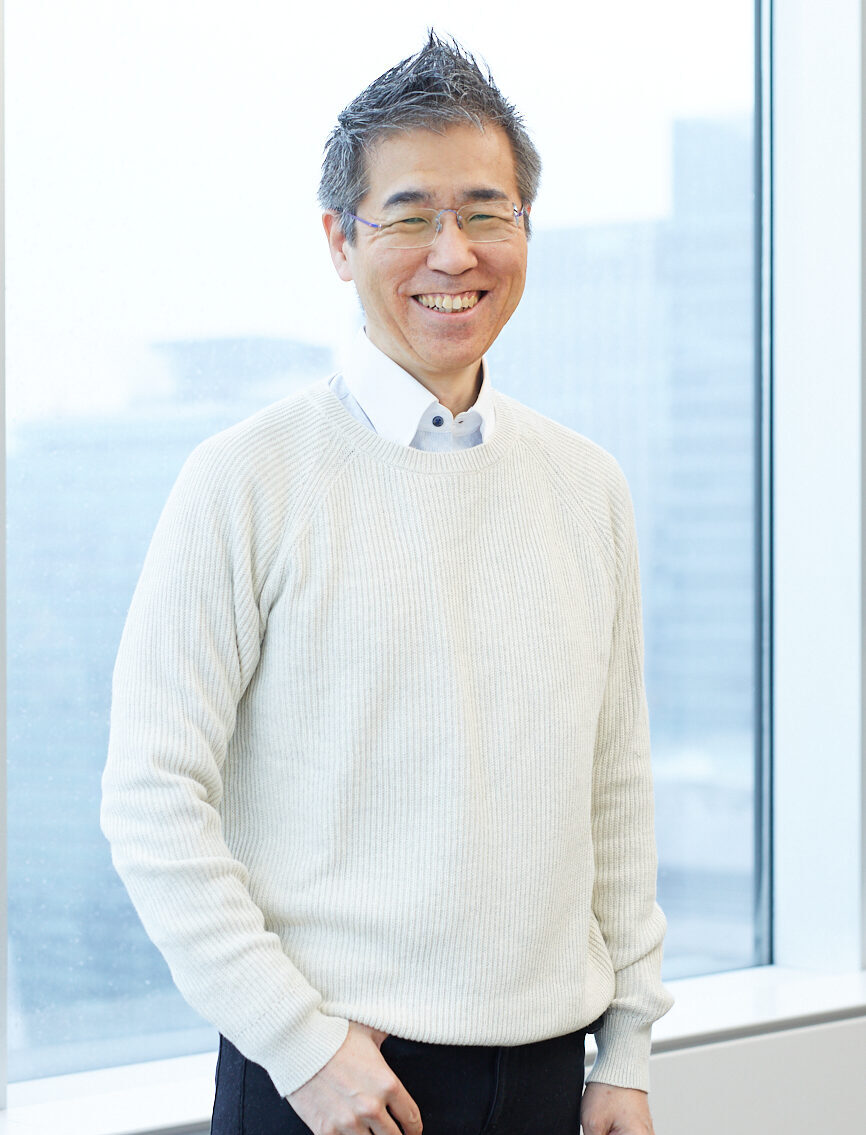 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。1.出願の流れ

実用新案について、登録までの具体的な方法を順に解説していきます。
1-1.先行技術調査
出願前には先行技術調査を行ないます。調査を行なう理由は、すでに同じアイデアが公知となっていたり、登録されていないかどうかを確認するためです。
実用新案の審査は簡易なものであるため、実際には権利の有効性に乏しいアイデアでも登録が認められてしまうケースがあります。
そして登録後に無効審判などにおいて「新規性」や「進歩性」などの登録要件を満たしていないと判断されれば、権利が消滅してしまうこともあるのです。こうしたケースを回避するためにも、先行技術調査は入念に行なうことをお勧めします。
先行技術は特許情報プラットフォームで確認できます。
1-2.出願
出願書類には
- 願書
- 実用新案登録請求の範囲
- 明細書
- 図面
- 要約書
があります。明細書などの記入方法は1-1.で解説した先行技術調査において、類似するアイデアの記載方法を’参考にするとスムーズです。
出願時には、「出願手数料」と3年分の「登録料」を一緒に特許庁へ支払います。
出願方法は、電子出願もしくは書面による出願です。2021年4月現在、実用新案における電子出願の割合は97%。ほとんどの出願者が電子出願を選択していることがわかります。
一方、書面による出願の場合、追加料金として電子化手数料が加わります。出願後、1ヶ月程度で出願者に対して出願番号が通知されます。
1-3.審査
1-1.でも触れた通り、実用新案の審査はあくまで形式的な要件のみが対象となっています。2つの形式的な審査が行なわれ、それぞれの審査において要件を満たしていれば設定登録が認められます。
基礎的要件の審査
出願内容が公序良俗に違反したものではないか、一件の出願に対して含めることのできる範囲を逸脱していないか、書類に著しい不備がないかなど、主に書類の記載においてルールが遵守されているか否かについての確認が行なわれます。
方式審査
方式審査では、出願書類や出願に関する手続きが法令で定められた方式要件を満たしているか否かについての確認が行なわれます。たとえば、実用新案は「物品の形状、構造、または組み合わせ」であることが要件として定められています。
特許では「製品の製造方法」や「医薬品の構成要素」などの登録も認められていますが、実用新案では認められる技術が狭い範囲に限定されているのです。出願書類において、こうした要件を満たしているか否かが審査されます。
補正指令
審査で不備が見つかった場合、特許庁から手続補正指令書が届きます。この指令に対して所定の期間内に補正を行ない、不備が解消された場合は設定登録へと進むことができます。
期間内に補正を行なわなければ出願は却下されます。補正期間は、手続補正指令書が発送されてから60日です。
(※)手続き補正について
補正指令を命じられなくとも、自発的に出願書類を補正することができます。その場合は、出願日から1ヶ月以内が期限となります。
1-4.設定登録
審査を通過すると、晴れて実用新案権の設定登録がなされます。出願から設定登録にかかる期間は早ければ約2ヶ月ほどです。設定登録日から約2週間後、実用新案登録証が届きます。
実用新案権の存続期間は出願日から最大10年。出願時に支払う登録料が3年分までなので、4年目以降も権利の存続を希望する場合は登録料を各年ごとに支払う必要があります。所定の期間内に納付をしなければ、実用新案権は消滅します。
➡実用新案出願に必要な費用は?代理費用の相場も併せて解説
1-5.出願内容の公開
設定登録後、出願内容は「登録実用新案公報」にて公開されます。公開時期は、設定登録日から約3~4週間後が目安です。
出願日から1年6ヶ月後に公開される特許と異なり、出願から公開までの期間が短いことが特徴です。そのため、パリ条約の優先権を主張した外国出願や国内優先権制度の活用などを検討している場合には、実用新案ではなくあらかじめ特許出願をしておくことが望ましいでしょう。
2.権利の有効性の確認
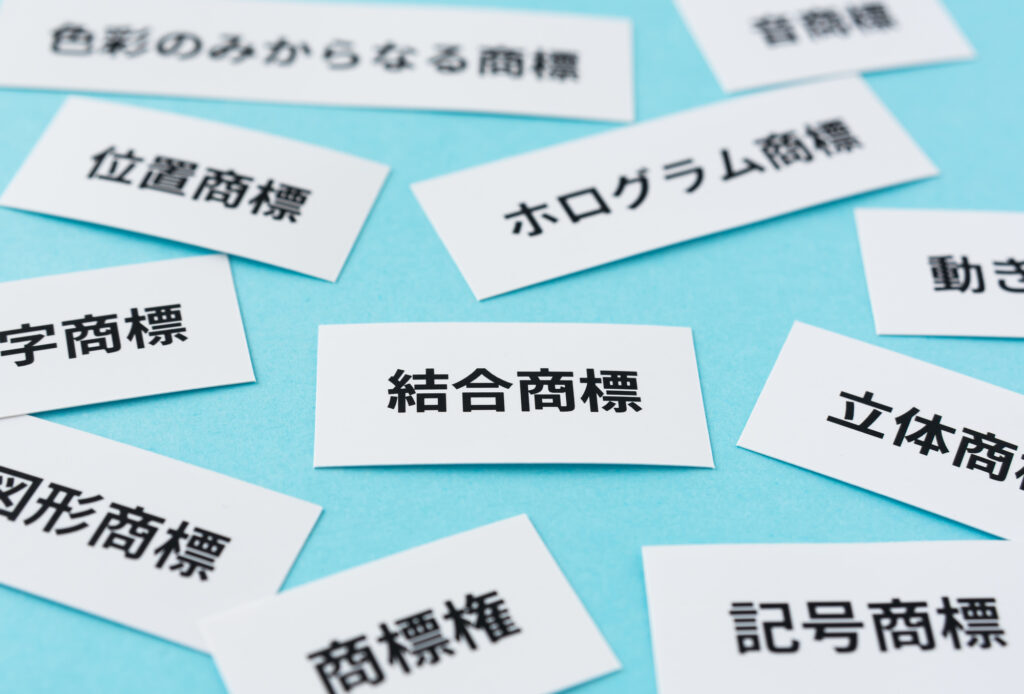
次に実用新案権の有効性を確認する手段や、第三者から権利が無効であるとの申立てが行なわれた場合の対処法について解説します。
2-1.技術評価請求
実用新案権を実際に行使したいと考える場合、まずは特許庁に「実用新案技術評価書」を請求する必要があります。権利を行使する具体例として、たとえば他者に対してアイデアの模倣を中止させたい場合などがあげられます。
1-3.で解説した通り、実用新案では「新規性」「進歩性」などの有無を問う「実体審査」が行なわれません。実用新案では、書類や手続き上の形式的な要件を満たしていれば設定登録が行なわれます。
そのため、実際には出願前から不特定多数の人々が目にすることのできる雑誌などに同一の技術情報が掲載されていたり、すでに同じアイデアが設定登録されていたりすることもあるのです。
そこで特許庁に対して技術内容の評価を請求し、権利が有効であることを証明してもらう必要があります。「実用新案技術評価書」において権利の有効性が認められれば、他者に対して警告し、模倣を中止させることができます。
この手続きを省き、後で権利が無効であるとの判断が下されてしまった場合には損害賠償請求の責任を負うことになるのです。また、そうしたリスクから回避できる確率を高め、権利の有効性を確かなものにするためにも、あらかじめ1-1.で解説した先行技術調査を入念に行なうことが大切であると言えます。
出願以降、技術評価書はいつでも請求できます。また、出願人や権利者だけでなく第三者でも請求することができます。さらに技術評価書は公開され、評価内容は特許情報庁プラットフォームで誰でも閲覧できます。
2-2.無効審判請求
無効審判請求とは、第三者が対象の実用新案権が無効であることを示す証拠を提出し、権利の無効化を要求する手続きのことです。
具体例として、たとえばあなたのアイデアを無断で模倣した製品を第三者が販売したいと考えているとしましょう。このまま販売すると権利侵害となります。そこで、第三者があなたのアイデアに対して「新規性」「進歩性」などの要件が乏しいとして、その理由を提出して権利の無効を訴えるのが無効審判請求です。
無効審判請求において権利が無効化されそうな場合、権利範囲である実用新案登録請求の範囲を減縮するなどの訂正をすることで権利の消滅を回避できる可能性があります。
請求の範囲の減縮は原則として一度だけ認められていますが、請求の範囲を拡大したり請求項を追加したりすることは禁じられています。
まとめ
短期間かつ簡易な審査でアイデアの権利を保持できる実用新案。登録のハードルが低いからこそ、まずは全体の流れを把握する必要があります。
そして審査でどのような要件が求められているのか、登録後にはどのような対処が必要となる可能性があるのかなど、重要なポイントを頭に入れたうえで万全の状態で出願に臨みましょう。