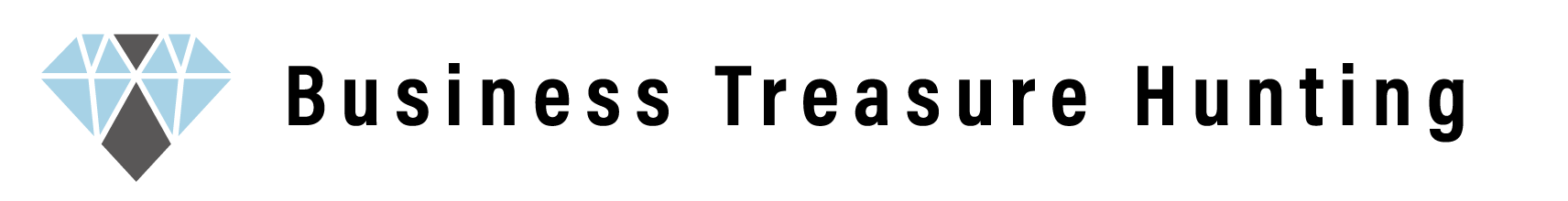人々の暮らしを少し良くするような、「ちょっとしたアイデア」の権利を保護するために出願されることの多い実用新案。特許よりも登録までのハードルが低いことから、自力で出願を検討している方も多いでしょう。
本記事では実用新案の出願において特許庁に支払わなければならない費用と、特許事務所に依頼した際に別途かかる費用の相場について解説します。
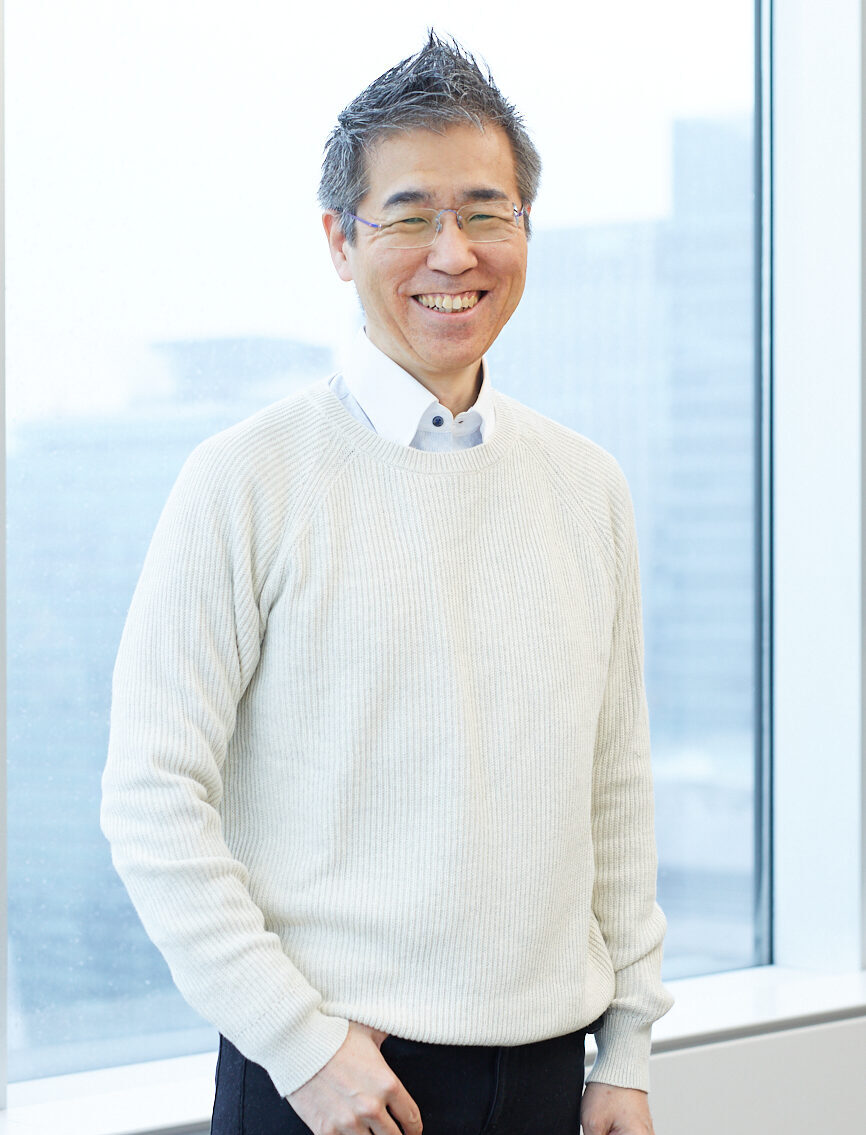 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。特許庁に支払う費用
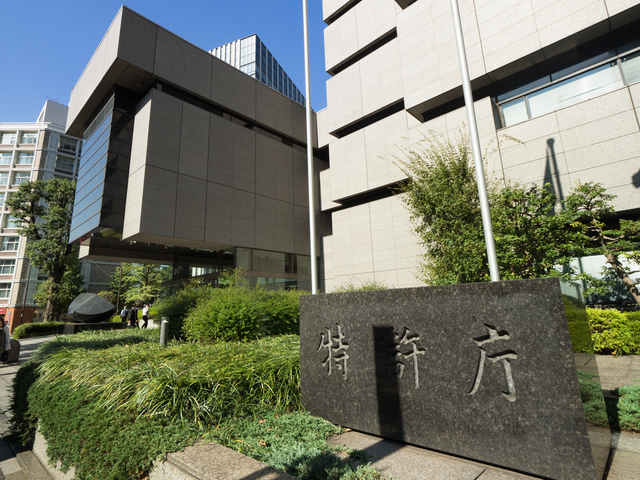
実用新案の出願や更新、技術評価書を請求した際などには、特許庁に所定の手数料を支払う必要があります。これらの料金は自力での出願と代行依頼による出願とを問わず、その手続きの際には必ず必要となる費用です。
1-1.出願料と登録料
実用新案では、出願の際に「出願料」と「3年分の登録料」を特許庁へ支払います。特許の場合は審査の結果、特許査定を受けて初めて登録料を払う手順ですが、実用新案の場合は最初に登録料も納付しなければならないことを覚えておきましょう。
「出願料」は14,000円、「登録料」は毎年2,100円+(請求項の数×100円)です。たとえば1件の実用新案に対して請求項の数が3の場合、第1〜第3年分の登録料は7,200円となります。
| 特許出願料 | 14,000円 |
| 登録料 | 毎年2,100円+(請求項の数×100円) |
1-2.権利の更新料
1-1.で解説した通り、実用新案では出願の際に「3年分の登録料」を特許庁へ支払います。そして4年目以降も権利を維持したい場合は、各年ごとに登録料を改めて納付しなければなりません。
実用新案権の権利存続期間は出願日から最大10年。第4〜第6年は1年ごとに(6,100円+請求項の数×300円)、第7〜第10年は1年ごとに(18,100円+請求項の数×900円)が必要です。出願の際に納付する第1〜第3年分とは料金が異なりますので注意しましょう。
| 第4〜第6年 | 6,100円+請求項の数×300円 |
| 第7〜第10年 | 18,100円+請求項の数×900円 |
1-3.技術評価書の請求費用
実用新案登録が行なわれたアイデアについて、その権利の有効性を確認するには「実用新案技術評価書」を特許庁に請求します。
技術評価において「新規性」「進歩性」などの要件を満たしており権利が有効であると判断された場合には、権利を行使し、他者に対して模倣の中止などを求めることができます。
通常、「実用新案技術評価書」にかかる費用は42,000円+(請求項の数×1000円)です。一件の実用新案において請求項の数が3の場合、45,000円となります。
また、特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願の場合、「実用新案技術評価書」にかかる費用は8,400円+(請求項の数×200円)。
特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願の場合、「実用新案技術評価書」にかかる費用は33,600円+(請求項の数×800円)となります。
| 技術評価書費用 | 42,000円+(請求項の数×1000円) |
| 特許庁作成 | 8,400円+(請求項の数×200円) |
| 特許庁以外 | 33,600円+(請求項の数×800円) |
特許事務所に依頼した場合の費用

特許事務所に実用新案の出願手続きを依頼した場合、1.で解説した費用以外にも代行手続き費用が発生します。
相談料
まだ実用新案を出願するかどうか迷っている段階での相談料は、特許事務所によって無料の場合と、相談料を設定している場合とがあります。
相場は0円〜1時間ごとに10,000円程度です。まずは相談してから検討したいという場合には、まず相談料について確認するところから始めてみると良いでしょう。
先行技術調査費用
実用新案は、出願前に同様のアイデアが登録されていないか否か、などを確認する「先行技術調査」を行なっておくと安心です。
他者の出願内容は、特許情報プラットフォームも確認できます。しかしながらアイデアの詳細な内容について、過去に一般に公開されている文献などで同様のものが存在しないか、など細部まで調査を行なう場合には専門知識が必要となります。
他者からの模倣など、実用新案登録後に権利を行使しなければならないケースを踏まえ、詳細な調査を行なう際には特許事務所に依頼することが望ましいでしょう。
「先行技術調査」も相談料と同様、特許事務所によって無料である場合と、調査費用が設定されている場合とがあります。相場は0円〜10万円程度と、調査の精度などによっても大きく異なります。
出願費用
出願の際にかかる特許事務所への代行費用は、
- 願書
- 明細書
- 実用新案登録請求の範囲
- 図面
- 要約」
の作成と出願手続きを含め、20万円〜35万円程度が相場です。請求項や図面の数などによって金額が変動するケースが多いです。また、特許事務所によっては1万円〜5万円程度の成功報酬が別途発生する場合もあります。
補正費用
審査で不備が見つかった場合の補正料金は、内容次第で金額が変動するケースが多いです。方式補正の場合、相場は1万円程度。一方、手続補正書の作成や提出手続きにおいては、2万円〜20万円程度と補正内容によって大きく異なります。
登録後の費用
実用新案の設定登録後も、4年目以降の登録料納付や技術評価書の請求、無効審判の対応などを特許事務所へ代行依頼することが可能です。
4年目以降の登録料納付の相場は1万円〜2万円程度。技術評価書の請求は3万円程度〜請求項の数によって変動します。無効審判請求の際の費用は、25万円〜35万円程度です。
| 4年目以降 | 料金相場 |
| 登録料納付 | 1万円〜2万円 |
| 技術評価書 | 3万円程度〜請求項の数 |
| 無効審判請求 | 25万円〜35万 |
特許事務所に依頼するメリット

ここまで実用新案について、自分で手続きをすべて行なったとしても必ず必要となる費用と、特許事務所などに代行依頼をした場合の費用について解説してきました。
特許庁に支払う出願料と登録料は特許と比較して安価であり、補正などを行なう場合でも追加料金はかかりません。せっかく安く済むのであれば、自力で手続きをしてしまったほうが良いと考える方も多いでしょう。
しかしながら、一見すると簡単に思える実用新案出願において特許事務所に依頼するメリットは多くあります。
無駄な出願を回避できる
たとえば、特許事務所ではこれから実用新案を出願しようと考えているアイデアが、実用新案できちんと効力を発揮できるか否かを相談できます。
出願内容によっては実用新案ではなく特許に適しているものや、権利化によって出願内容が一般公開されることでかえって権利者にとってマイナスになることなどもあるのです。
さらに、知見のある弁理士が先行技術調査を詳細に行なうことで、権利の有効性を高められると考えられます。実用新案の審査は形式的なものであるため、その権利を実際に行使するには技術評価請求を行なわなければなりません。
しかしながら、あらかじめ先行技術調査を仔細に行ない、出願書類の記載内容にも入念に気を配ることで、技術評価においても権利者にとって有利な評価結果を得られる可能性が高まります。
安定した管理が望める
1-2.でも解説した通り、実用新案権を4年目以降も維持するには各年ごとに登録料を特許庁へと納付する必要があります。しかしながら期日を忘れて登録料の支払いを怠ると、権利は消滅してしまいます。
確実に権利の更新をしたいと考えるなら、更新の手続きを特許事務所に任せることは有効な手段であると言えるでしょう。
また、審査で補正指令が通知されたり、他者から無効審判を請求されたりした際にも、特許事務所に代行を依頼すると対応がスムーズです。
まとめ
特許と比較して、安価な費用で出願ができる実用新案。特許事務所に手続きを依頼した際にも、他の知財権と比べて費用を安く抑えることができます。
実用新案でアイデアを出願しようかどうか迷っている方や、出願を決めたものの自力での出願などの手続きの代行を依頼するのかで迷っている方は、まずは無料相談などを受けてみるのも良いでしょう。