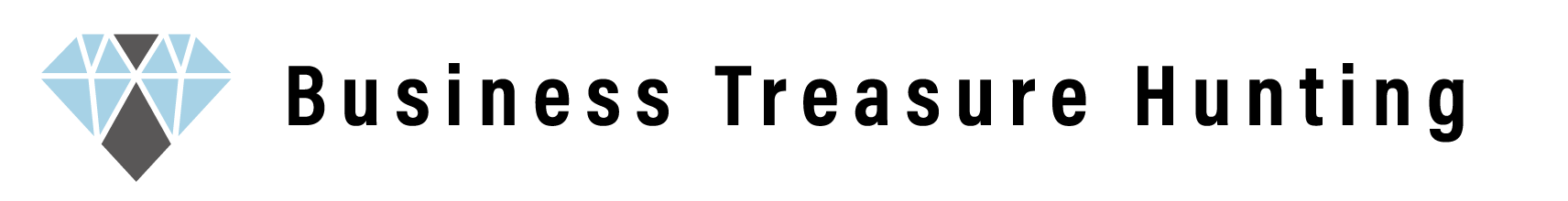ファストファッションでおなじみのジーユー(GU)。安価な価格帯と幅広いカラーバリエーション、ベーシックなデザインなどが支持され、老若男女を問わず高い人気を集めています。
そんなジーユーを展開するジーユー社に対し、IT関連企業アスタリスク(大阪市淀川区)が、2020年6月16日付で「特許権侵害行為」の差し止めの仮処分を大阪地方裁判所に申し立てました。訴訟の対象となっているのは、ジーユーの店舗で5月から導入が始まったセルフレジです。
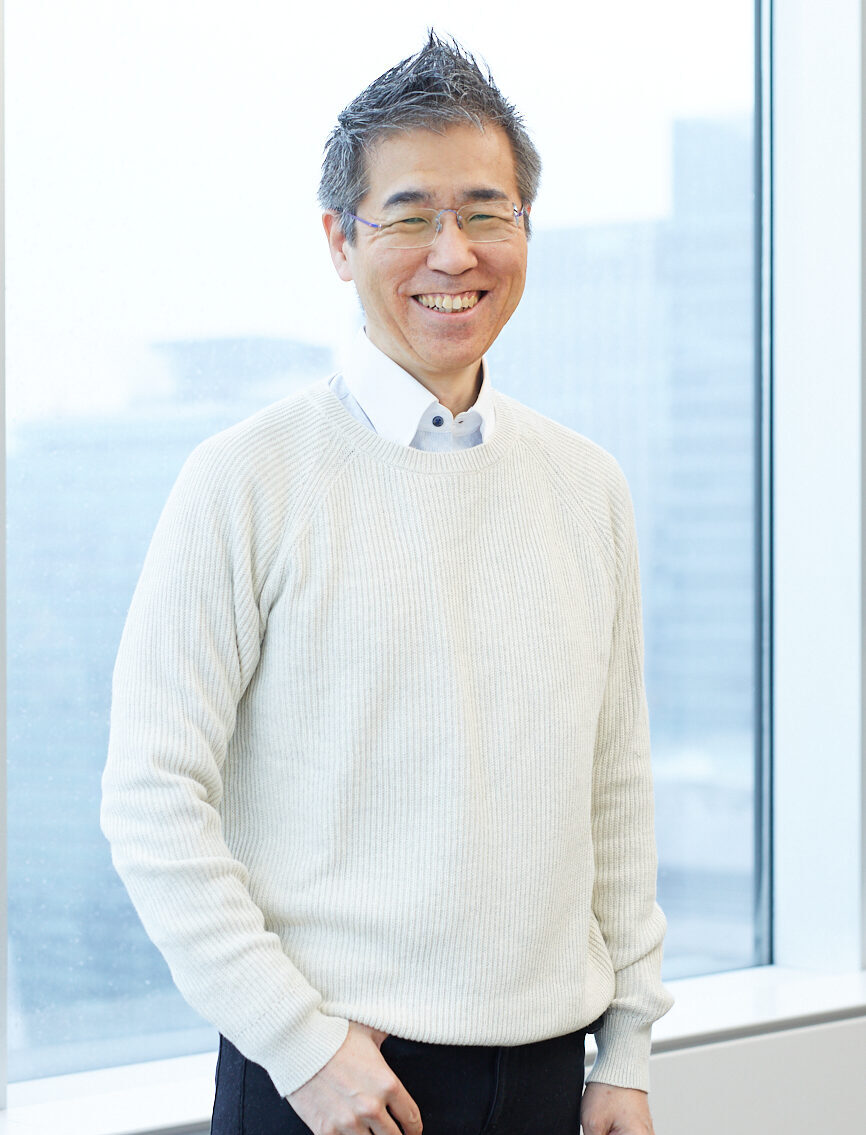 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。訴訟の概要

実は、アスタリスク社は、ジーユー社の親会社でありユニクロ(UNIQLO)を展開するファーストリテイリング社に対しても、2019年9月24日付で「特許権侵害行為」の差し止めの仮処分を東京地方裁判所に申し立てています。
実際に、ユニクロのセルフレジを使ったことがあるという方も多いでしょう。
操作は非常に簡単です。レジスペースのくぼみに商品の入ったカゴを置くだけで、バーコードをスキャンすることなく商品のICタグが自動で読み取られ、決済ができるという仕組みになっています。
アスタリスク社は、このセルフレジについて、ファーストリテイリング社に対して訴訟を起こしていました。しかし、現在も訴訟が続くなかで、今度はジーユーの店舗にも同じ仕様のセルフレジが導入されたことにより、ジーユー社に対しても同様の訴訟を行ったという経緯があります。
特許権侵害のポイント

この訴訟において争点となるのが、セルフレジの仕様です。
アスタリスク社が特許を持つセルフレジの特徴は、扉やフタなどで遮らなくても、カゴの中の商品IDを正確に読み取れるところにあります。
「カゴを置くだけで商品IDを読み取れるセルフレジ」自体は、他社でも開発・製造が進んでおり、決してアスタリスク社だけの独自技術ではありません。しかし、そうした従来のセルフレジは、電波漏れなどの影響から、周囲にいる人が持っている商品のIDまで誤って読み取ってしまう恐れがありました。
この問題を解決するために、大手コンビニのローソンではカゴを置いた後で蓋を閉じることで誤操作を防ぐ仕様のセルフレジを導入しています。
この仕組みであれば、アスタリスク社の特許を侵害することにはなりません。そして、実は今回新たに訴訟の被告となったジーユーにも、これまではローソンと同様の仕組みのセルフレジが設置されていたのです。
これに対して、アスタリスク社は、1件の特許出願を分割して関連特許5件を出願しており、すべて「開口が上向きに形成されたシールド部」を備えることが特徴になっています。
実際、扉やフタを閉める、というひと手間を掛けずに、置くだけで読み取りが始められるほうがユーザビリティに優れていることが分かります。
今回、GUに設置されていた従来型のセルフレジをわざわざ新型に置き換えた理由もそのあたりにありそうです。このように、構成はシンプルであっても、効果が目に見える特許は価値が高く、保護に値するといわれています。
両社の動向

そもそも、ファーストリテイリング社とアスタリスク社は、アスタリスク社が下請け企業としてiOS関連の製品を納入するという取引関係にあったといいます。
その後、2018年8月にファーストリテイリング社がセルフレジのコンペを実施し、アスタリスク社は同社へ10月に提案書を提出しました。しかし最終的には他社製品が選ばれ、アスタリスク社のセルフレジが採用されることはなくなったといいます。
アスタリスク社は、2019年1月にセルフレジに使用された技術である「RFID 読取装置関連特許」を取得しています。そして同年2月より、ユニクロの店舗で訴訟の対象となるセルフレジが導入され始めたのです。
以来、アスタリスク社は自社の特許技術がユニクロのセルフレジに活用されているとして、ライセンス契約の交渉を進めてきました。
しかし、契約は成立せず、ファーストリテイリング社は同年5月、アスタリスク社の「RFID 読取装置関連特許」の「無効審判」を請求します。さらに、アスタリスク社に対してライセンス使用料をゼロ円にしてほしいという要望をファーストリテイリング社から提案され、交渉決裂に至った末に訴訟となったのです。
無効審判請求とは?
ファーストリテイリング社が行った「無効審判請求」とは、アスタリスク社の特許が無効であるという申し立てを行い、それが認められれば、結果としてファーストリティリング社は特許権を侵害していないことを主張するものです。
「無効審判請求」には、対象となる特許について、「新規性」や「進歩性」などに乏しいことを証明するための証拠資料が必要となります。
新規性とは?
「新規性」とは、従来知られた発明とは異なる発明であり、出願前に公開も公然実施もされていない技術である性質を指します。
出願前に発明した製品を公開したり、販売したりすれば、「新規性」は喪失されたと判断されます。「新規性」の有無の基準として、
- 「従来の技術とまったく同じであれば新規性なし」
- 「発明と従来の技術との間に、少しでも異なる点があれば新規性あり」
と判断できます。たとえば、あなたの勤める会社でスニーカーを新たに発明したとします。
従来の技術で開発されたスニーカーAは、本革素材で靴本体と同色の靴紐が付いており、裏返すと靴底の表面がギザギザとしています。
一方、新たに発明したスニーカーXは、本革素材で靴本体と同色の靴紐が付いており、裏返すと靴底の表面が平らで滑らかです。
スニーカーAとBでは相違点があるため、「新規性あり」と認められます。
進歩性とは?
「進歩性」とは、従来の技術や知識を持つ人が容易に発明できないことが基準となります。これまでに世間では発表されていなかった新たな発明であっても、それが従来の発明の単なる設計変更レベルのものであったり、従来の発明を単に寄せ集めただけのものである場合は、「進歩性なし」と判断されます。
訴訟のゆくえ
特許権とは、この「新規性」「進歩性」の両方を特許庁から認められた発明に付与される権利です。そこで、「無効審判請求」では、本当にその審査が妥当であったのかを調査します。
特許等の公開公報や専門雑誌などからも情報を集め、「新規性」や「進歩性」などが乏しいことを証明し、特許権を無効化させるのです。
もしもファーストリテイリング社の「無効審判請求」が認められれば、アスタリスク社は「RFID 読取装置関連特許」の権利を無効化されてしまいます。
そうなれば、もちろんファーストリテイリング社はライセンス使用料を払う必要がなくなり、アスタリスク社は特許に関する独占的な権利や、それに伴うメリットを失ってしまうのです。
両社の争いについては、下記の記事に現在の訴訟に関する進捗や懸念事項が詳細に記されています。
さまざまなメディアで取り沙汰されることにより、現在、ファーストリテイリング社やジーユー社は知財業界だけでなく、アパレル業界やエンドユーザーなど、多くの人々からその動向が注目されています。
動き方次第ではブランドイメージの低下に繋がる可能性も否めないため、慎重な判断が必要とされるでしょう。
一方、アスタリスク社にとっても一連の争いは大きなダメージとなっています。裁判が長期化すればするほど訴訟にかかる費用が会社を圧迫することも考えられるためです。
さらに、ファーストリテイリング社による「無効審判請求」の審決予告では、請求項1~4のうち、3つの請求項が無効であると判断されました。しかし、残り1つの請求項については無効とならなかったため、アスタリスク社の特許は一部を認 められたことになります。
今後は無効であると判断されなかった請求項の構成要素を、ファーストリテイリング社のセルフレジが持っているかどうかが争点となるでしょう。
さらに、審決予告で無効と判断された請求項においても、アスタリスク社側は60日以内に訂正をすることができます。アスタリスク社の訂正によって特許全体が無効となることを免れれば、無効と判断されなかった請求項が残り、審理を継続できるのです。
※訂正請求では、新たな発明特定事項の追加や、権利の拡張は禁止されています
ファーストリテイリング社の敗訴

2021年5月20日、知的財産高等裁判所においてファーストリテイリング社が敗訴しました。この背景には、ファーストリテイリング社側による無効審判請求が深く関わっています。
無効審判請求の判決を覆した審決取消訴訟
3-1.で解説した通り、無効審判請求とは当該特許に「新規性」「進歩性」が乏しく、特許が無効であることを申し立てるもの。本請求において無効審判請求を提訴されたアスタリスク社は2020年8月、4つの請求項のうち3つが無効であるとの判決を受けていました。
これに対しアスタリスク社は、知的財産高等裁判所に対して審決取消訴訟を提起。さらに無効と判断された権利範囲においても審決内容を踏まえて新たな特許を取得するなどの対応を重ねてきました。
この動きを受け、知的財産高等裁判所は2021年5月20日に審決取消訴訟の判決として「1〜4まですべての請求項が有効である」──つまり当初の判決を覆し、本件におけるアスタリスク社の当該特許がすべて有効であることを言い渡したのです。
この判決を受け、ファーストリテイリング社は2021年6月2日に最高裁判所へ上告を行ないました。アスタリスク社は引き続き争う構えを見せています。
終わらない訴訟の今後
アスタリスク社としてもまだ安心できる状況ではありません。実はファーストリテイリング社からアスタリスク社への無効審判請求は二度行なわれています。
ファーストリテイリング社は2020年8月に下された1〜4の請求項のうち3つを無効とする判決を不服とし、二度目の無効審判を請求していました。本来、無効審判請求は一つの案件に対して再び同じ証拠を提出して訴訟することは認められていません。
しかしながら本件ではファーストリテイリング社から一度目とは異なる証拠が提出されたことで、二度目の無効審判請求の申し立ても受理されたという背景があります。 この訴えに対し、知的裁判高等裁判所が2021年4月8日付けで「全請求項を無効にする」という審決予告を行なっています。
予告通りの判決が下された場合、アスタリスク社は再び審決取消訴訟の提起や、権利範囲のさらなる見直しなどを迫られるでしょう。 さらに審決取消訴訟で納得のいく判決が下されなかった場合には最高裁判所への上告の必要もあり、アスタリスク社の体力面も不安視されています。
まとめ
ファーストリテイリング社の従業員数は、5万6661名(2020年2月29日現在)。対して、アスタリスク社の従業員数は、88名(海外子会社含む、2018年8月末日現在)。
誰もが知っている大企業と、大阪を拠点とする中小企業では、今後、後者の訴訟における体力面や経済面が心配になってきます。また、訴訟にかかる費用面の影響も含めて、特許訴訟は、大企業にとって有利な展開に進むことも珍しくないのが実情です。
しかし、時間とお金と労力をかけて取得した特許権が「無効審判請求」により簡単に覆ってしまえば、審査をした特許庁の信頼に関わりますし、苦労してまで特許を取得しようという考えに至らなくなる企業が増えてしまうでしょう。
実際のところ、このような表立った訴訟に至るケースの10倍、100倍の数の知財紛争が水面下の「交渉」により解決されていることも見逃せません。
両社の争いがどのような決着を迎えるのかを注目しつつ、客観的な審査により、公正な判断が下されることを願います。また、特許を含む知財活用の究極の姿の一つである訴訟の帰趨を見つめることにより、普段の知財活動やこれを活用した事業開発戦略の参考としたいものです。
参考元:株式会社アスタリスク公式HP