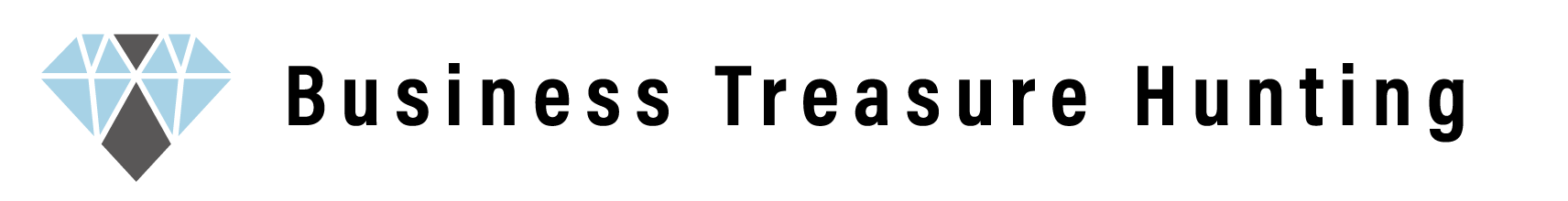近年、多くのスタートアップ企業が特許をはじめとする知的財産の重要性を認識し、積極的な知財戦略に取り組んでいます。一方で、知的財産に対して「大企業が保有するもの」といったイメージも根強くあるでしょう。
しかしながら、認知度が浅く資本力や人員の限られたスタートアップ企業にとって、知的財産は今や事業展開を軌道に乗せ企業を成長させるために決して無視できない存在です。
本記事では知的財産の中でも特許に着目しました。スタートアップ企業の成長を促す存在として、特許がどのような役割を果たすのか、その重要性やメリット・デメリットについて解説します。
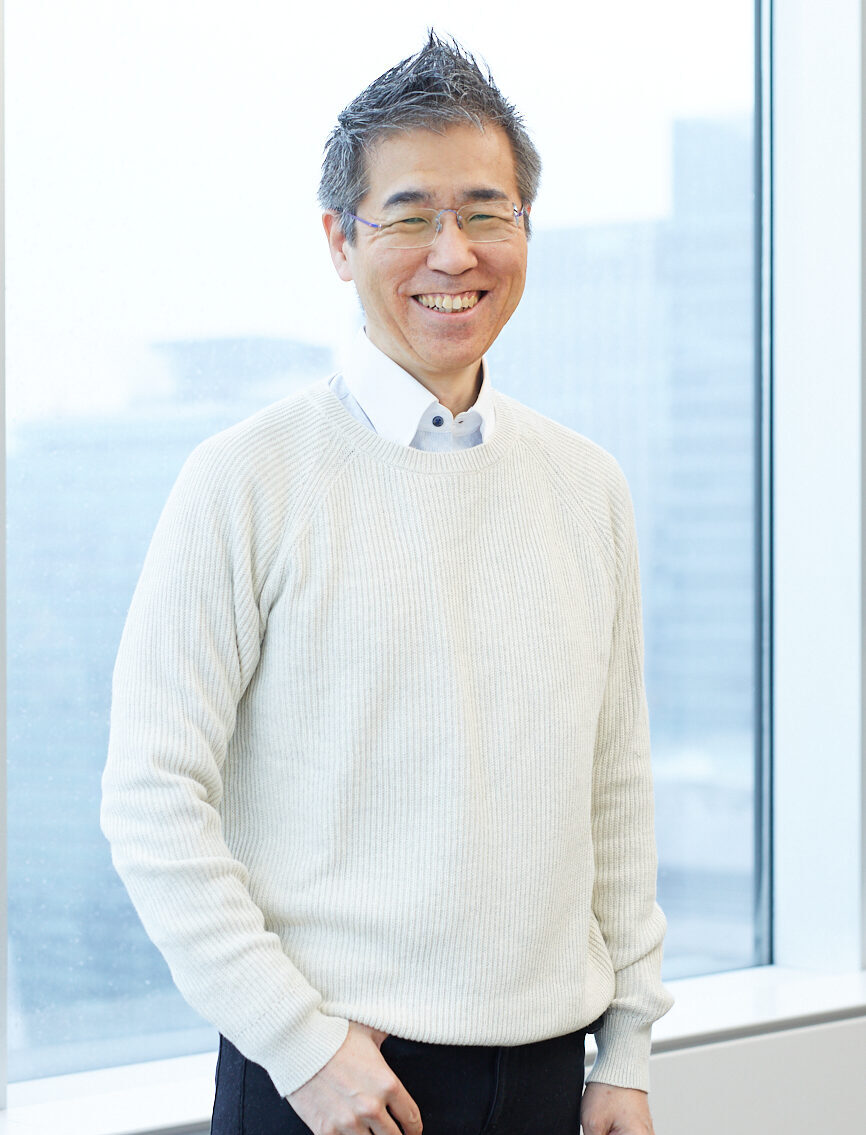 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。1.スタートアップを成功させるには?

スタートアップの成功において大切なのは、事業領域や技術において「競合優位性を高めること」です。しかしながら競合優位性と一言に言っても、その戦略は企業の規模や事業形態によってさまざま。
たとえば大企業であれば、安定した品質の製品を低コストで大量に生産することができます。一方、資本力や人員の限られたスタートアップ企業ではこうした量産体制に太刀打ちすることは難しいでしょう。
そこで注目したいのがスタートアップ企業ならではの独創的なアイデアと尖った技術力です。たとえ小さな市場であっても、まだ誰も着手していない領域で専門的なサービスや製品を生み出し、それらの事業が評価されれば企業への注目は高まります。
2.競合優位性を高める手段としての特許取得

1.で解説した「競合優位性を高める」ためには、その事実を客観的に証明できることが求められます。なぜならどんなに革新的な技術であっても、その技術の素晴らしさをすべての人が正確に理解できるわけではないためです。
製品やサービスに対する評価は「企業の認知度・信頼度」によって簡単に左右されます。さらに、これまでに例がない技術であればあるほど、第三者は「その技術がどう凄いのか」を判断することが難しくなります。
うしろだての少ないスタートアップ企業ほど、そうした傾向が顕著に表れるでしょう。せっかくの技術が的確に評価されないまま同業の大企業に模倣され、これまでの研究開発に投資した資金や工数が台無しになってしまう危険もあるのです。
3.そもそも特許とは?

特許とは「これまでにない革新的かつ産業の発展に寄与する高度な発明」です。発明者や権利者が特許庁に対して出願を行ない出願内容が認められると、発明を独占できる特許権が与えられます。
特許を取得すると、第三者は権利者の許可なしに発明を利用することはできません。そのため権利者は発明を独占したり、他者に発明の利用を認めてライセンス料を得たりするなど、事業を優位に進めることができます。
特許権を無断で侵害された場合、権利者は侵害企業に対して損害賠償の請求などの手段に踏み切ることができます。
特許の保護期間は最長20年間です。保護期間が切れると、誰でも発明を自由に使えるようになります。
4.スタートアップが特許を取得するメリット3選

それではスタートアップ企業が特許を取得すると、どのようなメリットを得られるのかについて解説します。
他社の市場参入や模倣の抑制ができる
特定の市場において特許を取得すると、同じ市場で事業展開を計画していた他社は参入を躊躇するようになります。
なぜなら発明の過程で特許権を侵害する恐れがあったり、すでに発明内容が特許と重複していたりすれば大きな損害を被る可能性があるためです。さらに、意図的な模倣も防ぐことができます。
こうしたケースでは、他社は結果として特許の領域外で新たな事業開発を検討したり、それが難しい場合には市場への参入自体を諦めたりします。
あるいは、正式にライセンス料を支払ってでもその発明を利用したいという企業があれば、新たな利益にも繋がるでしょう。
事業提携により大企業や成長企業とのパイプができる
特許を取得した発明が他者から非常に魅力的な発明であると評価された場合、事業提携を持ちかけられることがあります。
こうしたケースでは大企業や成長企業からの事業提携が見込めることもあり、資本の限られたスタートアップ企業であっても名だたる企業と対等に渡り合うための武器を手に入れられるのです。
相乗効果でより高度な発明ができる
特許を取得することでクロスライセンスに繋がり、さらなる技術力の発展や事業の拡大に繋げられる可能性もあります。
クロスライセンスとは、知的財産権の権利者同士が互いの保有する知的財産権の使用を許諾し合うことです。このケースでは、互いにライセンス料を必要としない契約を結ぶことが多いとされています。
本来であれば使用に障壁のある発明が相互に利用できることで、自社だけでは難しかった技術を使ってさらなる発明へと発展し、さまざまな製品やサービスを生み出すという相乗効果が期待できるのです。
5.スタートアップが特許を取得するデメリット2選

次に、スタートアップ企業が特許を取得するデメリットについて解説します。
大きな費用や工数がかかる
特許を取得するには「出願料」「出願審査請求料」「登録料」などの規定の金額を特許庁へと支払う必要があります。また、知識がない状態で出願書の記載や拒絶理由通知への対応などをすることが困難なこともあり、多くの企業や団体・個人は特許事務所を通じて代行を依頼します。
出願内容や特許庁の審査状況によっても異なりますが、特許事務所へ手続きを依頼した場合の費用は800,000円〜1000,000円程度が相場です。
また、特許は出願から権利取得までに平均で1年2ヶ月程度の期間がかかります。さらに弁理士に手続きを依頼した場合でもすべての工程を丸投げできるわけではなく、出願準備や拒絶理由通知への対応などにおいても入念な打ち合わせが必要となるため、時間的拘束も視野に入れておかなければなりません。
発明内容がオープンになる
特許を出願すると、特許権を取得できてもできなくても、出願日から1年6ヶ月後に出願内容が特許広報で公開されてしまいます。特許公報は全世界の誰もが閲覧できます。
つまり、「特許権を取れないまま自社のノウハウが全世界に公開され、発明を模倣されたけれど権利がないので訴えることもできずに利益を横取りされる」という最悪のケースも考えられるのです。
さらに国内で取得した特許権は、日本以外の海外では通用しません。そのため公開された発明内容が海外企業に模倣されても、日本の特許権しか持っていなければ権利を行使することはできないのです。
ちなみに、全世界共通の特許権というものは存在しません。海外からの模倣を抑止したい場合には、各国で特許権を取得する必要があります。その際には、一度に複数国の出願手続きを簡略化できる国際出願制度が便利です。
6.資金調達にも特許は役に立つ?

資金調達フェーズのスタートアップ企業にとって、特許の取得はとても重要な意味を持っています。2.で解説した通り、どれだけ優れた技術であってもその素晴らしさを万人に評価されることは容易ではありません。
特許は技術力を客観的に証明する手段として非常に有効であり、権利を保有していれば他社の模倣による利益損失を未然に防ぐことができます。この概念を投資家たちは念頭に置いています。
そのため、すでに特許を保有していたり、積極的な知財戦略に取り組んでいたり、「特許出願中」の発明があったりすることを評価材料にしているのです。
実際に、健康管理に特化したウェアラブルデバイスを展開するフィットビット社(2007年5月創業)などは資金調達の直前に特許出願を集中的に行なっています。
これは資金調達前というタイミングが投資家へのアピールになると共に、資金調達に成功するという一定の道筋が見えたからこその大きな動きともいえるでしょう。
7.まとめ
特許権の取得には決して安くない費用や時間もかかることから足踏みをしている方も多いでしょう。しかしながら自社を飛躍させるための大きな一歩として、今や特許は欠かせない知的財産であるといえます。
特許は技術力の客観的な証明だけでなく、企業への対外的な評価においても重要な意味を持ちます。新興市場で新たな事業を展開する際に躓かないためにも、まずは自社の発明に関連する特許について理解を深めてみられてはいかがでしょうか。
この記事の参考資料
デイライト法律事務所
StartupDrive
知育特許事務所