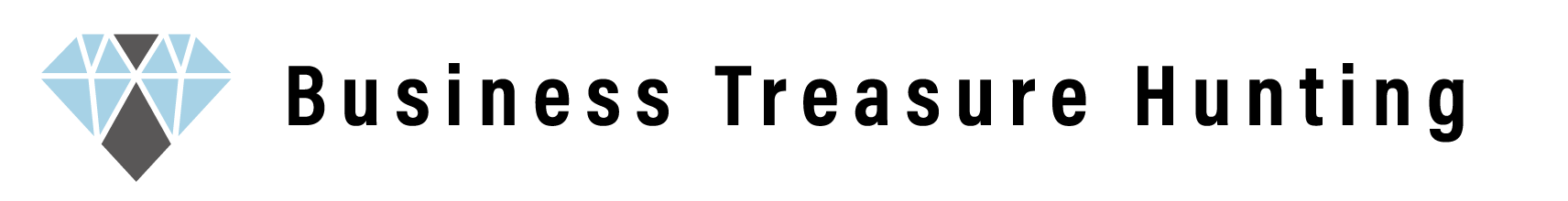商標はロゴマークやネーミングなど、その商品やサービスが自社のものであることを識別するための目印。他社の模倣を抑止したり、ライセンス契約を結んだり、といった権利を得るためには商標登録をしなければなりません。この記事では商標権の取得にあたって必要な準備や手続きと、企業の動向について、実例をまじえて解説します。
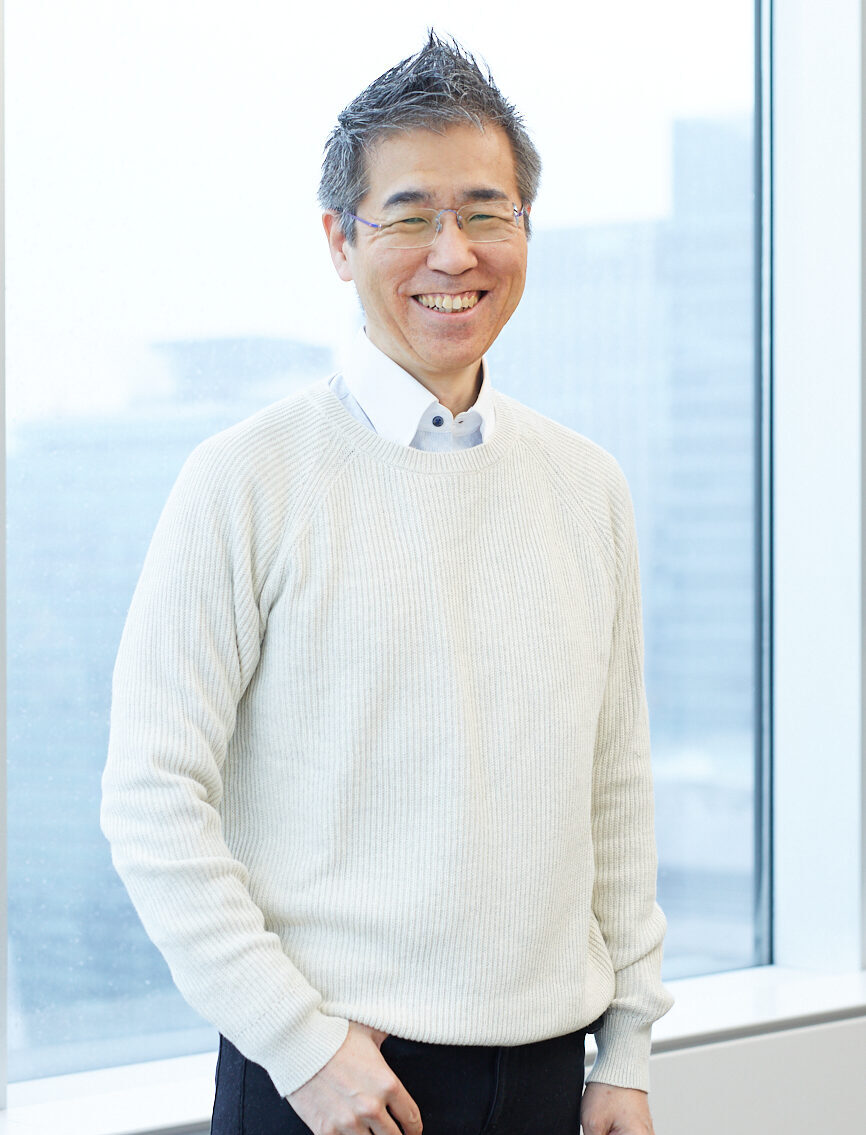 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。商標取得前にすべきこと

商標権を出願するには、事前調査や確認が重要です。いずれも自社のイメージや価値を損なわないために万全を期する必要がありますので、決して怠らないようにしましょう。
先行商標調査
自社商品の発売を控え、早めに行なっておきたいのが先行商標調査です。たとえば、あなたの勤める会社で新たな自社商品の発売が決まったとしましょう。発売に先駆けて商品名の商標登録出願を試みましたが、特許庁に拒絶されてしまいます。なぜならほぼ同一のネーミングで他社が商標登録を行なっていたからです。

このケースではあなたの勤める会社は原則として自社商品のネーミングを変更するしかありません。ほぼ同一のまま発売を強行すると、商標権の侵害で訴訟されてしまう恐れがあるためです。
仮に訴えを起こされなかったとしても、先に商標を登録していた企業や、商品を偶然手にとった消費者からの印象は悪くなってしまうでしょう。商標権の侵害は「知らなかった」では済まされない問題なのです。
こうしたトラブルは「商標を考案する際に」調査をすることで抑止できる確率が高まります。
※当事務所では新商品の商標を考案する「ネーミング・ブレスト」と、その場で商標弁理士が登録可能性を調査する「ライブ商標調査」の同時開催が好評です。関係者がみな腹落ちしてかつ登録可能な商標が決まります。
登録が認められない商標の確認
次に確認しておきたいのが、自社の商標が「基準を満たしているか否か」です。商標は出願しても必ず登録されるわけではありません。商標権の取得には調査や手続きを経て特許庁の審査を通過することが必須事項です。実際に以下のような商標が「登録できない」と商標法で定められています。
産地や品質などを表示しているに過ぎない商標
商標は自社と他社との商品やサービスを区別するものです。そのため、たとえば福岡県産のトマトを販売する際の商標として「福岡県」の文字や、福岡県の地図の図形だけを表示したものは審査で拒絶されてしまいます。
また、マッサージなどで「体質改善」の文字を登録しようとしても、効能を表しているだけで他社との識別が図れるものではないため登録が認められないのです。
公益に反する商標や誤認を生じさせる可能性のある商標
たとえばあなたが個人的に沖縄土産としてグッズの販売をしたいと考え、沖縄県の県庁マークを商標出願しても審査で拒絶されてしまいます。公益的な団体や事業などが管理する商標を一個人や一企業が独占することは不適当であると考えられているためです。
また、オレンジ果汁100%の飲料であるにもかかわらず「○○レモンジュース」というネーミングで商標権を得ることもできません。商品を手にとった消費者がレモンジュースであると誤認してしまう恐れがあるためです。
他社の商品と混同の恐れがある商標
1-1.でも解説したとおり、すでに登録されている商標と同一または類似した商標は審査で拒絶されてしまいます。「マークが同一または類似であり、指定商品・指定役務も同一または類似である」という2つの要素が揃った際には商標権を取得できないのです。
指定商品とはリンゴであれば「果実」、パソコンであれば「コンピュータ」といった商品の分類です。指定役務とはサービスの内容のことでありホテルであれば「宿泊施設の提供」といった分類になります。
また、指定商品や指定役務が同一または類似ではなくとも、商標が有名なブランドロゴなどと誤認されてしまう可能性が考えられる場合には登録が認められません。
業務に関連しない、使用予定のない商標
商標は自社の事業で現在使用している、または使用を検討している業務と関わりのあるものでなければなりません。たとえば医師免許を持っていないのに指定役務を「医業」で出願しても拒絶されてしまうでしょう。
指定商品・指定役務が明確でない商標
商標権は権利の範囲が明確に求められます。そのため機能や役割において適切な区分が指定されていなければ登録が認められないのです。適切な表示・区分については、特許庁ホームページ「類似商品・役務審査基準」およびJ -Plat Pat「商品・役務名検索」で確認できます。
企業の商標取得に向けた動き

ここでは行政のサポートを受けて商標権におけるリスクを回避できた企業の事例を紹介します。
窓口への相談でトラブルを事前回避
外構工事、左官工事、ガーデンクリーニング、除雪などを手がける株式会社池元(石川県)。同社は初めて商標登録を行なった際、先行調査がいかに重要であるかを実感したそうです。
前述のとおり、同社のメイン事業は工事やクリーニングなどの施工が中心。近年では現場管理用コンピュータソフトウェアの提供も手がけています。
このソフトウェアは当初は社内で使用する目的で構築したのだそう。現場の管理監督者がリモートで作業情報の確認や指示ができたり、建築主などの関係者に対して現場状況を共有したり、といった目的で活用していました。
同社の事業所にはもともとさまざまな企業が出入りする機会があり、次第に同業他社を中心に「これはいいね」という好評価の声が増えていったそう。そこで正式にソフトウェアとして販売することを決めたそうです。
ソフトウェアの製品化に伴い、商品のネーミングとロゴマークは外部のデザイナーに一任。同社は開発・販売に専念するべく、ソフトウェアの技術面の相談のために知財総合支援窓口を訪れました。
しかしながら窓口で状況は一変。使用する予定だったネーミングとロゴマークが他社の権利を侵害する可能性があるとの指摘を受けてしまったのです。
そして窓口で弁理士への無料相談なども活用し、やはり権利侵害の可能性が高いとの結論に至りネーミングを変更することになりました。
このケースでは、もしも窓口を訪れていなければ出願のためにかけた時間や費用が台無しになっていたかもしれません。そうなれば発売の時期を延期させなければならなかった可能性も考えられるのです。
また、当初の相談目的であったソフトウェアの技術面に関しても、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「中小企業等特許情報分析活用支援事業」を紹介されたそう。他社の特許と抵触する可能性の有無を無料で調査してもらうことができました。
ソフトウェアの開発・販売事業や商標登録など、一度に初めての経験を積んだ同社。窓口への相談を通じてトラブルを回避でき、権利侵害における先行調査や検討の重要性を学ぶことができたと語っています。
まとめ
出願前にもさまざまな調査や準備を必要とする商標登録。知財の専門部署がない中小企業などでは、事前知識のない状態で不安を感じることも多いことと思います。
特許庁のホームページやJ -Plat Patを活用して先行商標調査などを進めつつ、不安なことやわからないことがあれば、気兼ねなく行政の窓口や専門機関へ相談してみてはいかがでしょうか。社内では見落としていた権利抵触の可能性や、権利範囲の課題などに気付けるかもしれません。