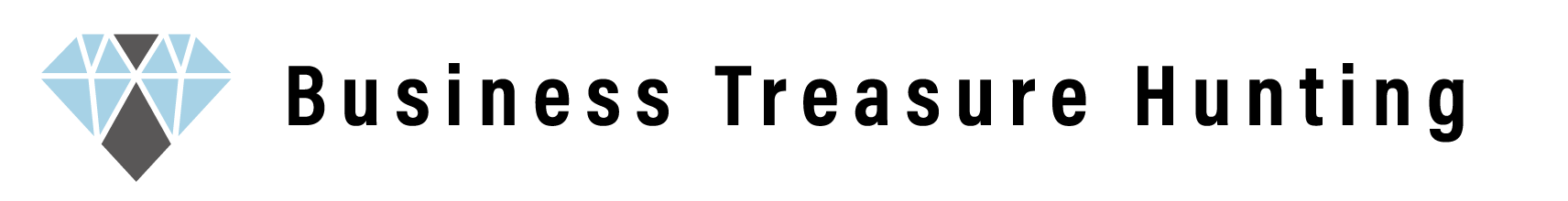「事業拡大に向けて特許を取りたい。でも、専門家に頼むお金がもったいないから、自分で申請できないかな?」この記事を読んでいる方の中には、このようにお考えの方もいるでしょう。特許を自分で申請する場合の方法や費用について、専門家に依頼した場合と比較しながら解説します。
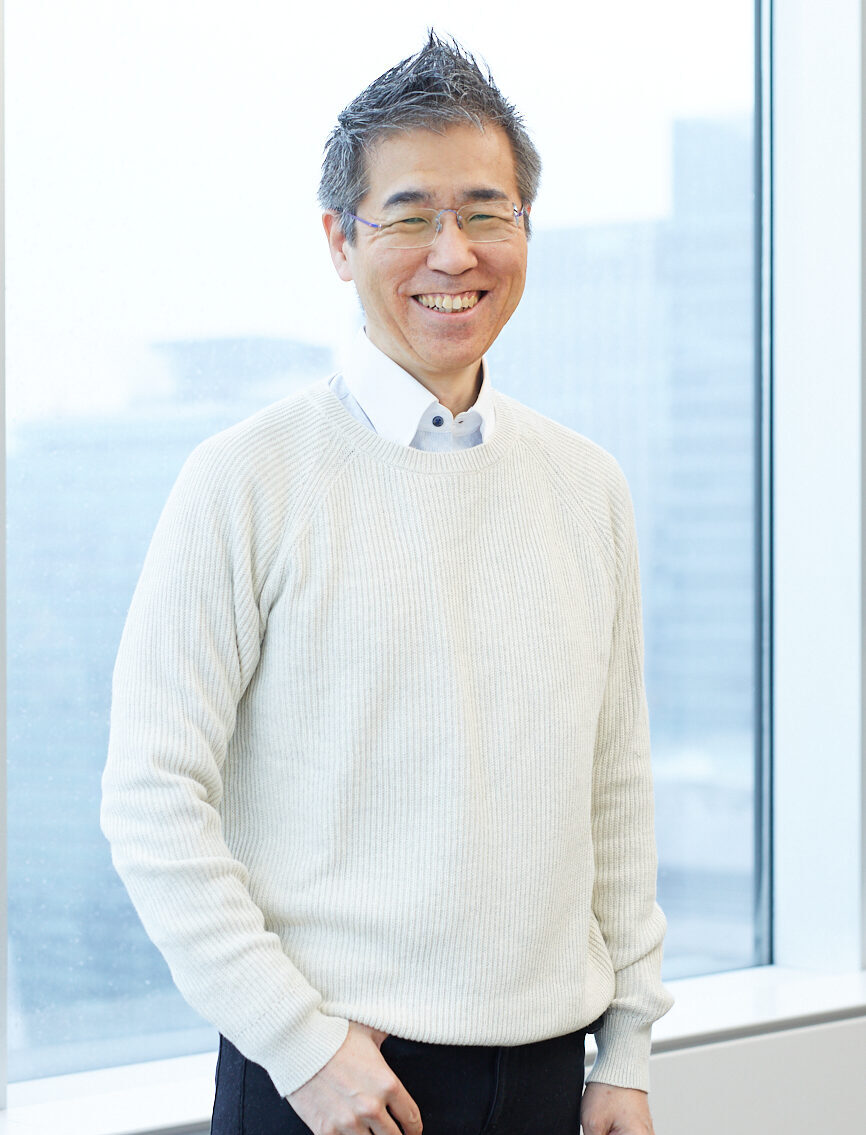 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。特許出願は自分でできる?

結論から言えば、申請・出願を自分ですることは可能です。出願の手続き自体に特別な資格などは必須ではありません。しかしながら、可能であるからと言っておすすめであるとは言えません。
なぜならば出願時や審査中において専門知識のなさから誤った選択をしてしまうことにより、特許が認められないケースが多いためです。
特許出願を自分で行なう際の方法と費用

専門家を頼らず、自分で出願する際の手順と費用について解説します。
先行技術調査
特許出願の前に、対象の発明と同じ、あるいは非常に似た案件がすでに出願されていないかを確認しましょう。特許は「新規性」「進歩性」という2つの要素が重視されており、「まだ一般に知られた発明ではないこと」「同業界の専門家などが簡単に考えつかない発明であること」が求められます。
そのため、すでに同じ発明が出願されている場合には特許が認められません。仮にそのことを知らずに出願して審査で認められなかった際も、出願時の手数料は返ってこないのです。
さらに、同じまたは非常に似た発明が特許としてすでに認められている場合、そのことを知らずに対象の発明を利用した製品やサービスなどを公開することで、権利侵害を問われて訴訟を起こされる可能性もあります。
こうした懸念点があるため、特許を出願する際には事前に技術調査をくまなく行ないましょう。先行技術は特許庁で公開されている「特許情報プラットフォーム J-Plat Pat」で確認できます。
さらに、「新規性」や「進歩性」を否定する技術文献は特許だけではありません。Webサイトなどで公開されている文献や、既に市場で提供されている製品やサービスなども、「新規性」や「進歩性」を否定する材料となりますので、これらも併せて調査しておく必要があります。
出願
特許の出願方法には、「紙の書類による出願」と「電子出願」の2種類があります。出願時にかかる費用は特許印紙代14,000円。また、「紙の書類による出願」の場合には電子化手数料が別途かかります。
電子化手数料は手続き1件につき1,200円+(700円×書面の枚数)です。1件の手続きで書面が5枚になった場合の手数料は4,700円となります。
出願書類
特許出願の書類は全部で5種類。
- 特許願
- 明細書
- 特許請求の範囲
- 要約
- 図面
という構成です。中でも「明細書」と「特許請求の範囲」には多くの労力がかかります。
「明細書」とは、発明の内容を第三者が見て理解できるようにわかりやすく記載したもの。「特許請求の範囲」とは、対象の発明がどこまでの範囲において効力を及ぼすのかを特定するためのものです。
「明細書」がきちんと書かれていなければ発明内容が理解されず特許取得を逃してしまいます。また、「特許請求の範囲」に誤りや見落としがあれば審査内容に影響するだけでなく、仮に特許を取得できても請求範囲次第では事業展開に支障をきたしてしまう場合もあるのです。
さらに出願書類の書き方には作法があり、その方法に則った書き方でないものは詳細な審査を受けることなく拒絶されてしまいます。
つまり出願書類を滞りなく仕上げるためには、「弁理士が把握している正式な作法」と「的確な請求範囲を見極めるための専門知識」が必要となるのです。
こうした知見は一朝一夕で得られるものではありません。そのため自分で出願を行なう際には、時間をかけて事前にこれらの知識について徹底した情報収集を行なう必要があります。
出願審査請求
特許は、出願後に自動的に審査が行なわれるものではありません。対象の発明の審査を希望する場合には、出願後から3年以内に出願審査請求を行なう必要があります。出願審査請求にかかる費用は特許印紙代138,000円+請求項×4,000円です。
意見書・補正書の提出
出願審査請求後、全体の8割の案件に対して届くとされるのが拒絶理由通知。特許が認められない旨の理由が記載された通知です。
しかしながら拒絶理由通知に対して「意見書」や「補正書」を提出することで改めて審査が受けられるようになります。「意見書」「補正書」は指定期間内に提出することが求められています。
「意見書」とは、審査官による審査に誤りがあることを意見するための書類。「補正書」とは、「明細書」や「特許請求の範囲」などの内容を補充・訂正するための書類です。「意見書」「補正書」については、特許庁の費用は不要です。
拒絶査定不服審判
拒絶理由通知に対して「意見書」「補正書」を提出しても審査内容が覆らなかった場合、特許庁から拒絶査定が届きます。拒絶査定が受け入れられず再び審査を請求したい場合は、拒絶査定不服審判を行ない一人の審査官ではなく3名または5名の審判官合議体による審理を求めることができます。
審判請求にかかる費用は、49,500円+(請求項の数×5,500円)。つまり請求項1項で55,000円3項で66,000円となります。
審判は準司法的手続きにあたる行ないであり、地方裁判所での争いと同等の扱いとなります。さらに、この審判でも結果が覆らない場合は知財高裁で争うこととなります。つまり、出願時以上に専門的な知識と判断が必要になると言えるでしょう。
特許取得
審査で特許が認められると、特許査定が届きます。この特許査定を受けて特許料を払うと、晴れてあなたの発明が特許権として登録されるという仕組みです。
最初に支払う特許料は3年分。1~3年分の特許料は、毎年 2,100円+(請求項の数×200円)ですので、3年分で、特許料6,300円+請求項×600円であり、請求項が1項であれば特許料の費用は6,900円。請求項が10項であれば12,300円となります。
さらに4年目以降も特許を継続したい場合には更新費用が必要です。期限切れで放置してしまうと、せっかく取得した特許権が消滅してしまいますので注意しましょう。
自分で出願するメリット

自分で特許出願することで得られるメリットをまとめました。
費用が抑えられる
特許事務所に手続きを依頼する場合、出願時にかかる費用は特許印紙代も併せて約350,000円〜500,000円程度。さらに拒絶理由通知などの対応を依頼すると、特許取得までにかかる費用は総額で約800,000円〜1,000,000円程度とされています。
一方、自分で手続きを行なう場合の費用は出願から特許取得まで、請求項が1項の場合は162,900円と、費用を抑えることができます。
知識が身につく
自力で手続きを行なうには、さまざまな専門知識や作法を学ぶ必要があります。そのため、事前調査を含め特許取得まですべてを自分で遂行することができれば、個人や企業において高いノウハウを蓄積していくことにもつながるでしょう。
自分で出願するデメリット

次に自分で特許出願することで考えられるデメリットをまとめました。
時間と労力
専門家に代行を依頼しないということは、すべての作業を通常の業務と並行して行なうということ。特許とは、相応の専門知識を持って出願や審査に挑まなければ、せっかくの費用がすべて水の泡になってしまいます。自分の本業以外の余暇に充てる時間や労力の大部分を費やさなければならないことを覚悟しましょう。
費用対効果
費用面に関しても注意が必要です。たとえば、自社の社員に出願業務を任せることで発生する人件費などが考えられます。普段の業務に加え、知識がなく慣れない状態での出願手続きや審査への対応を行なうには、残業代などの人件費が長期にわたって必要となる可能性が高いためです。
また、出願の手続きを自分で行なうことで出願への出費を最低限に抑えられたとしても、その期間に本業をおろそかにしてしまえば全体の利益を下げてしまい、結果としてマイナスになってしまう可能性も考えられます。
まとめ
「自分の発明のことは自分がいちばん理解している」「専門家とはいえ社外の人間に余計なコストはかけられない」など、特許出願を自分で行なおうと考える人の想いはさまざま。
しかしながら手続きに必要な知識や身につけておくべき作法は、決して単純明快であるとは言えないのが実情です。費用は請求項などによって変化し、それに応じてかかる時間や労力なども違ってきます。
まずは特許事務所に見積もりを依頼して予算と照らし合わせ、自分で手続きを行なう場合と、専門家に依頼する場合とのメリットを自分の目で比較してみてはいかがでしょうか。