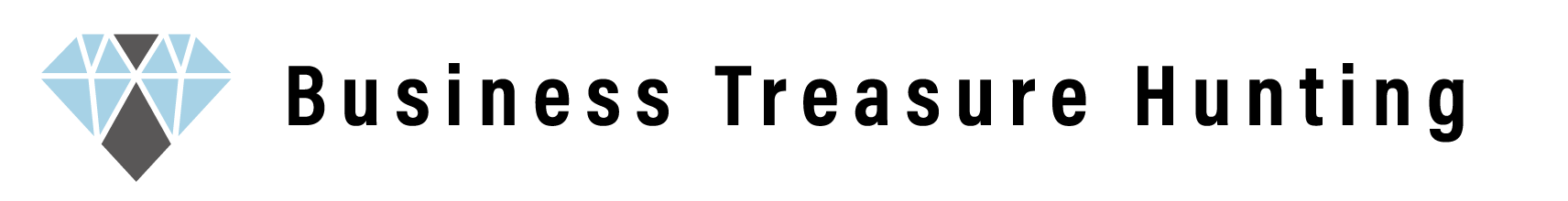特許権は取得までにさまざまな手続きと審査が発生します。また、事前準備から特許権を維持するための対応まで、審査の前後にも気を遣わなければならないことが多くあるのです。そこで、この記事では特許出願の流れと方法をステップごとにわかりやすく解説します。
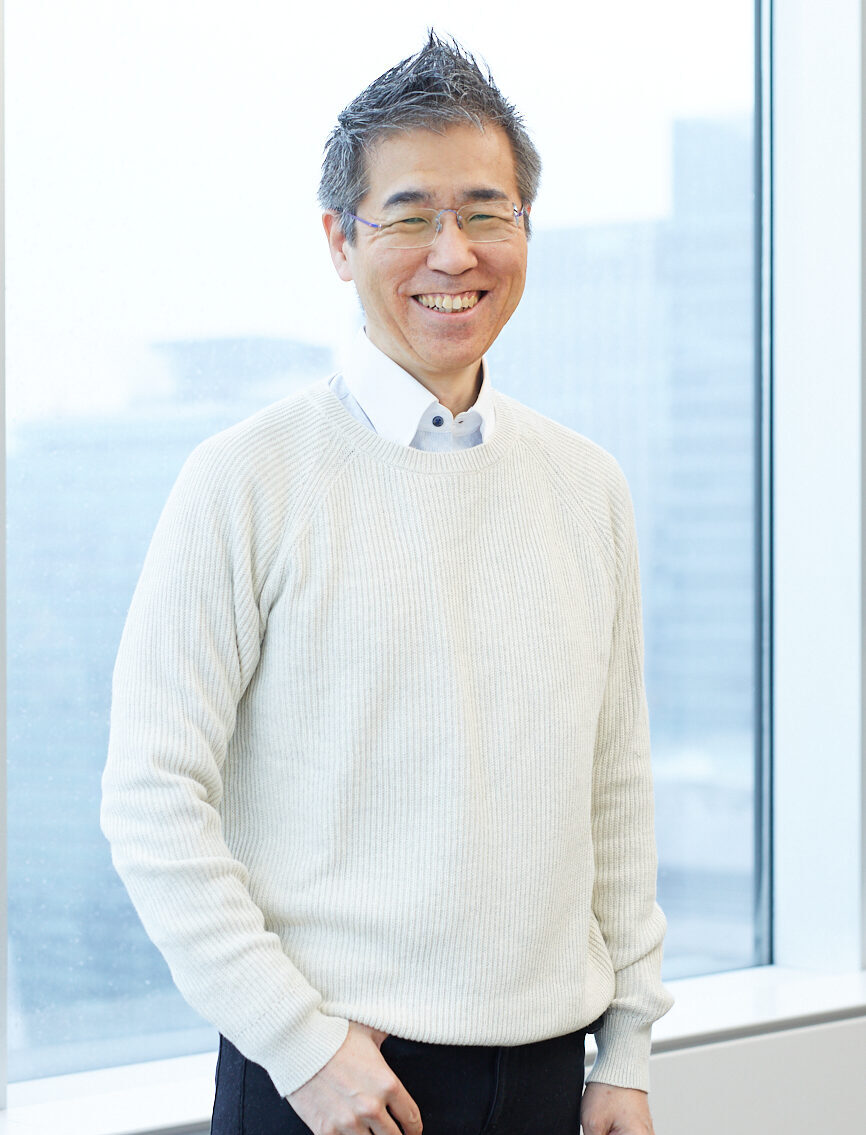 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。特許出願の流れ

特許は出願から権利を取得できるまでに、およそ2年〜2年半程度の期間をかける例が多いです。大まかな流れとしては、まず「出願書類の作成」を経て「出願」へ。
出願後は「方式審査」「実体審査」の2つの審査が特許庁で行なわれます。この審査中には、出願内容が基準や要件を満たさないと判断されるケースが多くあります。
その際には、補正書や意見書などを提出したり、それでも認められない場合には不服審判の手続きを行なったりするなど、特許庁に対して再び審査を請求することが可能です。
すべての審査を通過すると「特許査定」がなされ、特許料を納付すると晴れて「特許権を取得」できます。
特許権取得を目指す6つのステップ

それでは特許出願の流れで解説した特許出願の流れを6つのステップに分けて解説します。
1.出願準備
特許を出願するにはまず事前調査が必要です。対象案件と同じ技術がすでに特許出願されていないか?そもそも対象案件は特許の基準を満たしているのか?などを事前に確認し、調査内容をもとに請求権利の範囲や図面など、出願内容を精査します。
そして出願書類の作成。調査や書類の記入など、一連の工程は弁理士などの専門家に依頼するケースも多いです。専門知識のない人が自力で行なう調査よりも正確であり、出願書類を作成する際にも今後の事業展開を見据えた内容を作成してもらえるなど、メリットが多くあります。
2.出願
特許出願には2種類の方法があります。1つは書面による出願、2つ目は電子による出願です。書面で提出する際には、電子化手数料は手続き1件につき1,200円+手続き書面1枚につき700円がかかります。
現在、特許と実用新案の電子出願率は97%。特許庁としても電子化を推進していますので、コスト削減のためにも電子出願がおすすめです。
出願から1年6ヶ月が経つと、出願内容が一般公開されます。これは出願された順番に実施されるので、公開されたからといって特許を取得できるわけではありません。
3.方式審査
方式審査は、簡単にいえば書類チェックのための審査です。出願書類が書式通りに作成されているかどうかを特許庁に確認されます。この段階で不備があっても出願そのものが取り消されることはありません。
方式審査で不備が認められると「補正命令」が届きます。この補正命令に対して指定された期間内に補正書を作成し、提出することで再び審査を受けられるようになるのです。
4.出願審査請求
方式審査をクリアすると、次に実施されるのは「実体審査」です。ここで注意しなければならないのが、ただ待っているだけでは審査が行なわれないという点です。
実体審査を受けるためには特許庁に対して出願審査請求料を納付し、出願審査請求書を提出しなければなりません。出願審査請求が認められるのは出願日から3年以内。この期間を過ぎると出願が取り下げられたものと見做されてしまいます。
早く審査をしてほしい場合は迅速に出願審査請求を行なうことが大切です。一方で、開発段階の製品に関する発明であり、実際にその発明を利用するか否かが現段階では不明確な場合には、3年の猶予期間を活用して様子を見ることもできます。
5.実体審査
実体審査では、いよいよ出願内容が特許庁の定める要件を満たしているか否かをチェックされます。こちらも3.と同様に、要件を満たしていないと判断された場合でも、即座に出願が拒絶されることはありません。
特許庁により対象案件を特許化できないと判断された場合、「拒絶理由通知」が届きます。この通知には、出願内容において新規性や進歩性など、どのような要件を満たしていないのかが記載されています。
一度の実体審査で特許が認められる出願者は少なく、全体の8〜9割ほどに対して拒絶理由通知が発行されるともいわれています。
拒絶理由通知が届いたら、出願人は特許庁に対して「手続補正書」や「意見書」を提出して再度審査を請求することができます。期限は通知が届いた日から60日以内です。
手続補正書では特許の権利範囲を変更したり、発明の内容に変更を加えたりすることができます。一方、意見書は出願内容に拒絶理由が含まれないという反対意見を申し立てられる書類です。審査官が出願内容に対して誤った解釈をしている場合などに提出します。
手続補正書や意見書を提出しても拒絶理由が解消されない場合、「拒絶査定」が届きます。これに対して出願人は「拒絶査定不服審判の請求」ができます。期間は拒絶査定が届いた日から3ヶ月以内です。拒絶査定不服審判では、これまで審査を担ってきた審査官とは異なる審査官3名が特許を認めるべきか否かについて審理をします。
さらに拒絶査定不服審判でも特許が認められない場合の最終手段が知的財産高等裁判所への提訴です。期限は拒絶査定不服審判において拒絶審決が出されてから30日以内です。
6.特許権の取得
実体審査で拒絶理由がない、または拒絶理由が解消されたと判断されると「特許査定」がなされ、特許が認められます。これを受けて特許庁に3年分の特許料を納付すると、晴れて特許が登録され特許権が発生します。支払い期限は特許査定が届いてから30日以内です。また、特許が認められた発明は特許掲載公報に記載されます。
注意点としては、4年目以降も特許料の支払いを忘れないことです。特許権の存続期間は20年。これに対し、最初に特許が認められてから支払う特許料は3年分であるため、管理を怠って特許料の支払いをしないでいると権利は消滅してしまいます。
早く審査を受ける方法

通常、出願から特許取得までにかかる期間は2年〜2年半程度。しかしながら目まぐるしくニーズの変わっていく市場において、スピーディーな対応を求める企業は年々増えています。
こうした声に応えて2018年7月に開始されたのが「ベンチャー企業対応面接活用早期審査」と「ベンチャー企業対応スーパー早期審査」です。
ベンチャー企業対応面接活用早期審査
これはベンチャー企業の出願人が審査の前に審査官と面接ができる制度です。出願人は発明の特徴や戦略上の位置付けなどを審査官に対して直接説明することができます。
そして拒絶理由の有無や、拒絶理由がある場合の補正の示唆などを受けられます。この動きにより出願人は適切な権利範囲の請求に向けて、通常の審査よりも効率的に立ち回ることが可能です。この制度を活用すると、審査にかかる期間は3〜5ヶ月程度まで短縮されます。
ベンチャー企業対応スーパー早期審査
この制度では上記で紹介したベンチャー企業対応面接活用早期審査よりも短い期間で審査を受けられます。具体的には審査期間を2ヶ月半程度まで大幅に短縮することが可能です。
通常、すべての企業を対象としたスーパー早期審査では先行技術調査に基づく調査結果の充分な説明などが求められます。一方でこのベンチャー企業対応スーパー早期審査においては、出願者が把握している先行技術文献が事情説明書に記載されていれば、詳細な説明が緩和されるなどの優遇があります。
まとめ
出願前から権利取得後までさまざまな工程が必要となる特許権。調査や権利の維持・管理も含め、あらゆるシーンで専門知識が必要になってきます。
まずは権利取得までの6つのステップを把握し、専門家のアドバイスや早期審査制度なども検討しながら、出願までの一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。