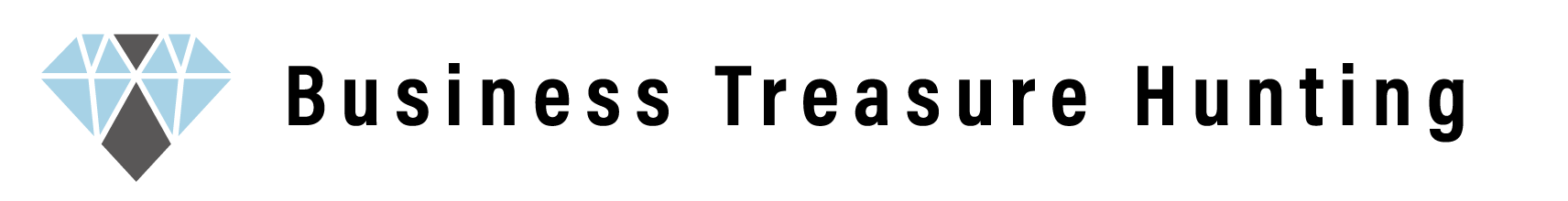自社の技術を模倣されたくない。独自の製品やサービスで市場のシェアを独占したい。特許を切り札に取引を拡大させたい。そのような多くの企業にとって重要な意味を持つ特許権。
しかしながら、自社の技術で特許を取れるのか、そもそもどのような案件が特許の対象となるのかを知らないという人も多いでしょう。この記事では特許を申請に欠かせない条件をまとめるとともに、出願前にチェックしておきたいポイントについても解説します。
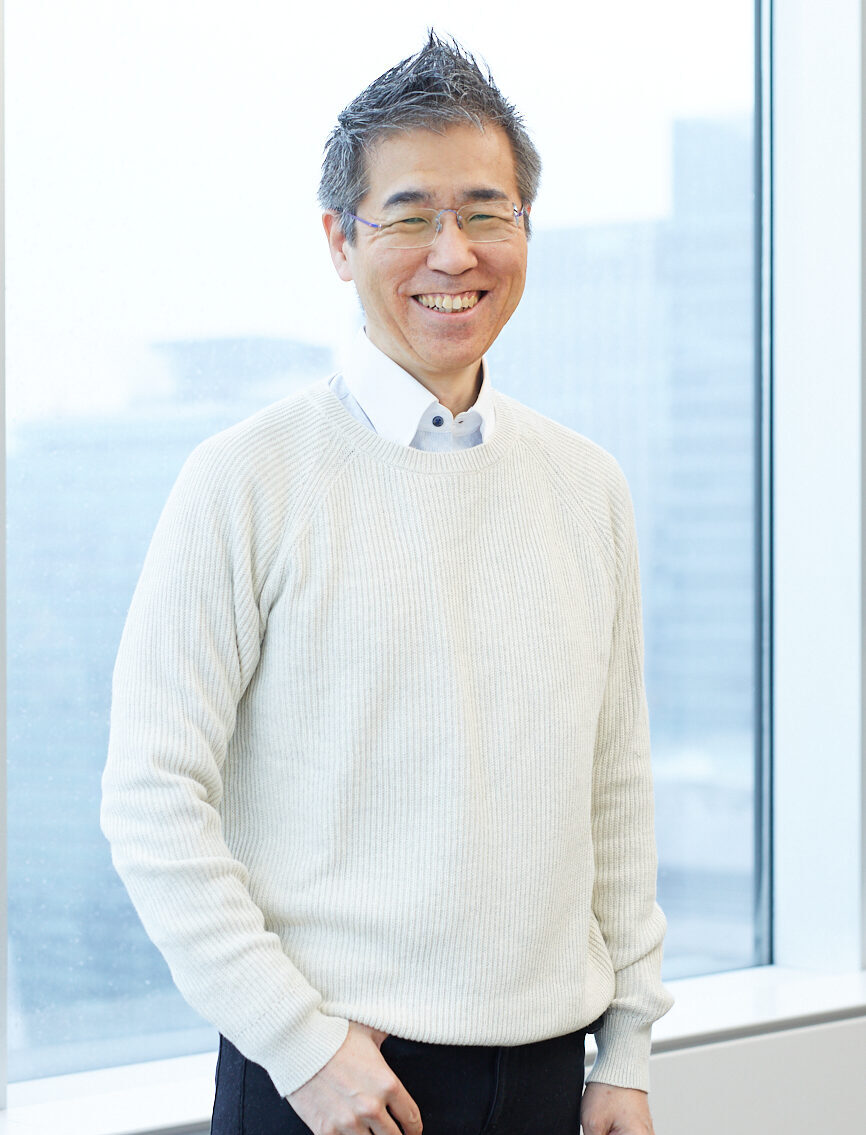 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。特許とは?

特許とは発明を保護するための制度のこと。特許が認められた発明者はその発明を独占したり他者にライセンスを認めたりすることができます。この権利が「特許権」です。
特許は出願日から1年6ヶ月後にすべての出願内容が公開されます。この制度により出願内容は特許庁の特許公開公報で誰でも全文を確認できます。
出願した順番に実施されるため、公開されたからといって出願案件が必ず特許として認められるわけではありません。また、特許権が適用されるのは出願日から20年。この期間を過ぎると誰もが自由にその発明を利用できるようになります。
特許申請の必須条件

特許は「斬新なアイデアであれば認められる」というものではありません。そもそも特許権の目的は、「発明者に権利を与えることで発明を保護しつつ、その発明を広く公開することで産業の発達に寄与すること」。
この目的を果たせなければ、どんなに斬新で画期的なアイデアでも特許の対象から外れてしまうのです。そこで特許申請における5つの必須条件をわかりやすく解説します。
産業において利用できる発明
特許権の最終目的は「産業の発達に寄与すること」。産業で利用できる発明とは、「実際に再現できること(=産業において量産でき、産業の拡大・発展に貢献できること)」が当てはまります。
生来の才能や訓練による努力など、人の先天的・後天的な能力によって実現の可否が左右されるものは対象外です。たとえばサッカー選手のロングシュートや、フィギュアスケート選手のトリプルアクセルなどと考えてみればわかりやすいでしょう。
また、人に対する医療行為も特許として認められません。高度な研究の成果による画期的な治療法であっても、それを特許にしてしまうことで権利侵害を恐れて人命救助行為ができなくなってしまうのを防ぐためです。
新規性のある発明
新規性とは、従来に存在しなかったものであるということを指します。つまり、すでに確立されている技術を出願しても特許権は与えられないのです。
たとえばゆで卵の作り方について、鍋で湯を沸かし卵を茹でる、といったごく一般的な方法を出願しても特許を取得することはできません。これはゆで卵を作ったことがある人なら誰もが知っているごく普通の製法であり新規性があるとはいえないためです。
調理済みのゆで卵は飲食店、小売店、量販店などさまざまな事業者が販売しています。基本的なゆで卵の作り方について特定の個人や団体に特許権を与えてしまえば、それらの事業者は明日からゆで卵を販売することができなくなってしまうでしょう。
もしくは権利者に対してライセンス料を支払い、ゆで卵の作り方を発明したわけではないのに特許を得た権利者だけが莫大な利益を得る不公平なビジネスモデルになってしまうのです。
進歩性のある発明
進歩性とは、その分野において専門家がなかなか考えつかないものであるということを指します。新規性のある発明で解説した新規性とも共通する部分がありますが、進歩性においては「意外性」や「技術の組み合わせによる作用」などが重視されます。
特許は「技術Aと技術Bの組み合わせ」や、「技術Cに含まれる成分Cと成分Dの調合方法や成分そのものを変更する」といった「従来の技術への変更」でも権利が認められることがあります。
しかしながら少しの変更を加えたからといって、それらに軒並み特許権を与えてしまっては世の中が特許だらけになってしまいます。そうなってしまっては多くの企業が権利侵害を恐れて技術を使わなくなり、産業が停滞してしまうでしょう。そうした本末転倒ともいえる状況を回避するための条件なのです。
言い換えれば、「技術Aと技術Bの組み合わせ」などでもその組み合わせに意外性があり、課題を解決するものであり、産業の貢献に寄与するものであれば特許が認められるケースも多くあるのです。
実現性のある発明
産業において利用できる発明で解説した内容にも通ずるポイントですが、特許に出願する案件は実現できるものでなくてはなりません。論理上は実施可能でも、「こんなことができたらいいな」という願望だけで実際には誰も実現できないアイデアなどは認められません。
たとえばポケットを叩くたびに中のお菓子が2倍、3倍と増えていく仕組みで特許を取ると考えてみます。この場合、叩いたポケットの中でお菓子がどのような状態になり、どのような経過で増えていくのかといった回数ごとの統計が必要になるでしょう。
また、お菓子の種類、ポケットの材質、叩き方、力量、叩く手の大きさや厚み、などを詳細に記述する必要があります。さらに「ポケットを叩くと存在しなかったはずのお菓子が倍増していく」ことに繋げるための理論を科学的に証明し、再現できなければなりません。
特許化すべきでない発明
特許は対象の発明を保護してくれる制度ですが、特許化することで発明者にとってかえって不利益となるケースがあります。まずは、特許化が有利になる案件。
これまでにない発明であっても、市場に流通され分解や分析をされてしまえば製造法が明確になるもの。この場合、他社に模倣され安価で模倣品を販売されシェアを奪われてしまうため特許を取ることが重要です。
一方で、特許化が不利になる案件。たとえば市場に流通されても他者には製法や成分が正確に特定できないもの。コカ・コーラやケンタッキーフライドチキンなどは自社の看板商品のレシピを特許化していません。なぜなら特許出願することで、他者には特定の難しいレシピが出願公開制度により全体が公開されてしまうから。
加えて20年の期間を過ぎればその権利は役目を終え、誰もが自由にコーラやチキンをレシピ通りに製造・販売することができるようになってしまうためです。
このように特許化すべきもの、すべきでないものの見極めは企業の未来を左右する重要な事柄です。たとえば製造方法は秘匿して市場のシェアを維持し、検査方法だけを特許化することでライセンス料を得るなど、その背景に応じた知財の使い分けが肝となります。
出願前のチェックポイント10選
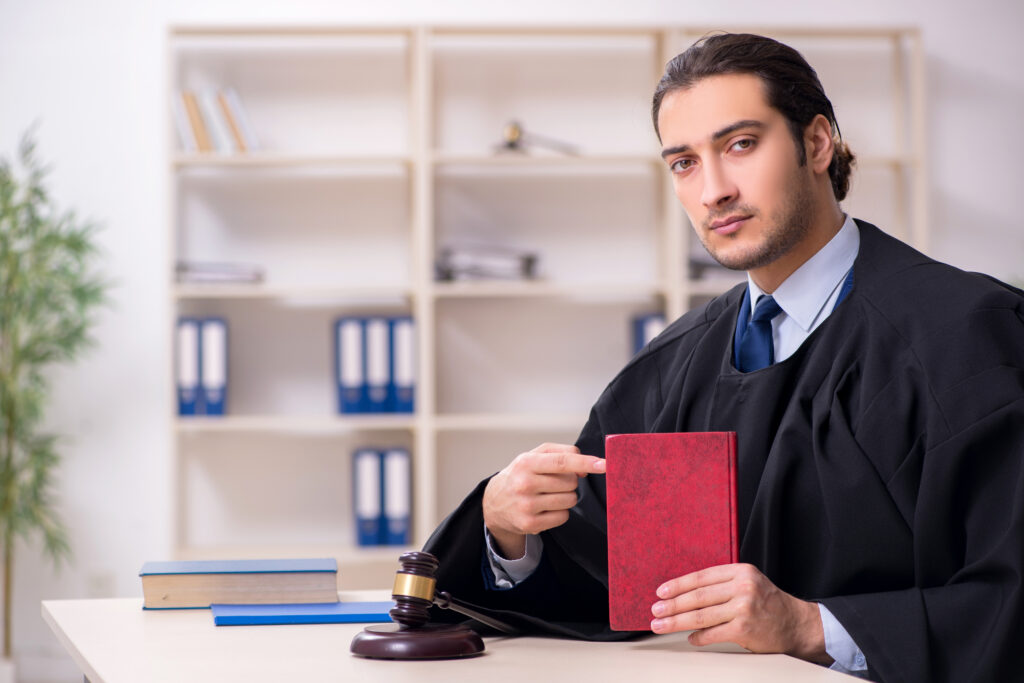
特許出願には事前の技術調査が必要です。しかしながら調査には時間を要し、専門家に依頼する場合には費用もかかります。まずは対象の発明が以下の10個のポイントに当てはまるかどうか確認してみましょう。一つでも該当する場合は早々に出願内容を見直してみるのもいいかもしれません。
- アイデアはあるが具体的な実現に至っていない
- 同じ技術を使った製品やサービスをメディアで見た
- 過去に同じ技術が出願されていた
- すでに発明内容を発表したり、その技術を使った製品やサービスを提供済みである
- 産業に活かすつもりはなく、個人で利用する範囲に留めたい
- 発明を実際に使うつもりも他者に使用を認めるつもりもない
- 人に対する診断や治療、手術方法に直結したものである
- 製品の製造過程で他者の特許が必要になる
- 他者に分析されても、正確に模倣される恐れがない
- 特許を得る利益と取得および維持のコストとの比較をしていない
まとめ
特許はシェア独占による売上増、信頼性向上による取引先の拡大など、さまざまなメリットをもたらします。いまや特許はネームバリューのある大企業だけのものではありません。まずは自社の技術が特許に適しているかを考えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。