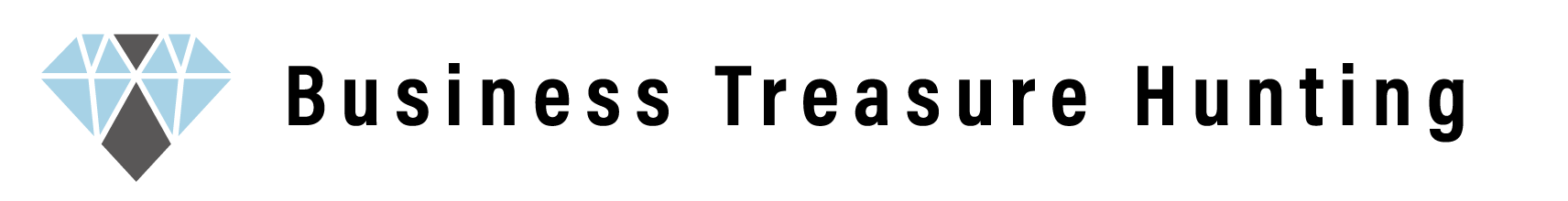企業や団体、個人のアイデアを短期間かつ簡易な審査で保護できる実用新案。特許などと比較し、費用や手続きにおいて申請のハードルが低いことから出願を検討している方も多いのではないでしょうか。この記事では、そんな実用新案の出願前に押さえておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
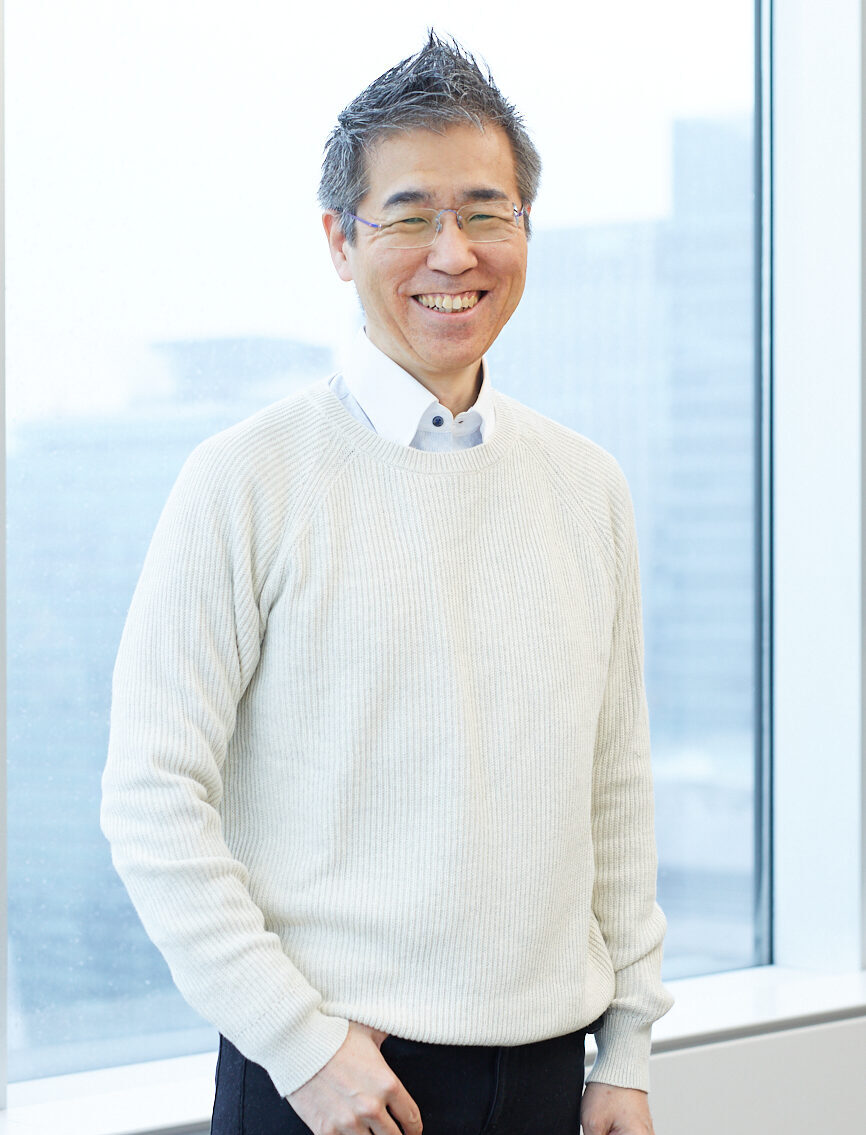 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。1.権利を維持するには?
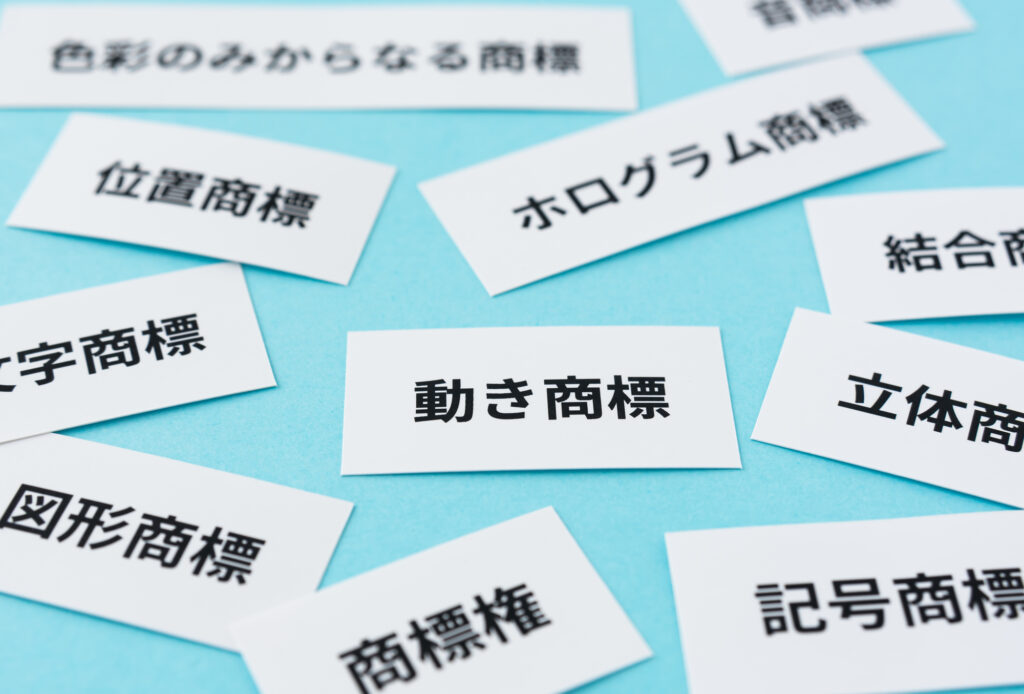
実用新案は、登録の際に3年分の登録料を支払います。そのため後述する無効審判を請求されて権利が無効になるなどの問題がなければ、登録後3年間は権利を維持できます。
そして4年目以降も登録料を支払うことで、権利を引き続き維持できます。権利の存続期間は出願日から最大10年間です。
4年目以降の登録料は1年ごとに支払います。また、支払いは権利を更新する前年以前に納付することが定められています。納付期限は実用新案の設定登録日が基準です。
つまり、4年目の登録料はすでに初年に3年分が納付されているため、設定登録日から3年以内に支払わなければなりません。
それ以降は1年ごとの更新となるため、たとえば5年目以降も権利を維持する場合は、4年目の権利が有効とされている期間内に登録料を支払うことになります。
納付期限内に登録料を納付しなければ権利は消滅します。
- 権利の存続期間の満了日は出願日
- 納付期限は設定登録日が基準
- 納付期限内に登録料を支払わなければ権利が消滅してしまう
この3つのポイントを忘れないようにしましょう。
2.設定登録や出願内容の公開までにかかる期間は?
実用新案は、手続きに不備がなければ出願から平均2〜3ヶ月程度で設定登録が完了します。また、設定登録の約1ヶ月後には出願内容が公開されます。つまり、早ければ3ヶ月ほどで出願から登録、公開まで一連の流れが完結するということになります。
設定登録・公開が早いことで考えられるデメリットは?
短期間で比較的容易に権利を保持できるのが実用新案のメリットですが、こうした迅速なスピード感がデメリットになることもあります。
たとえば、国内優先権を主張して出願する場合、先の実用新案出願がすでに登録されている場合には認められません。そのため、出願から半年ほど経ってから請求の範囲を広げるために国内優先権を主張した出願を行ないたいと考えても、平均2〜3ヶ月程度で設定登録が完了してしまう実用新案では、この制度を活用することができないのです。
また、外国出願の際にも、基礎出願となる実用新案の出願内容が公開されていることを理由にパリ条約の優先権が認められず、拒絶される可能性も考えられます。
一方、特許であれば出願後に出願審査請求してから登録を含む査定までに平均で15ヶ月(2020年度)の期間を要します。さらに、特許であれば出願から公開までの期間は1年6ヶ月です。
そのため、国内優先権や外国出願を少しでも検討している場合は時間の猶予がある特許での出願をすることが望ましいでしょう。
3.登録された実用新案が他者に模倣されてしまったら?

実用新案登録された自分のアイデアが他者に模倣されてしまったら、まずは相手に模倣を中止させることを考えるでしょう。
しかしながら、実用新案制度では他者の模倣が判明した場合でも、すぐに正当な形式で権利を主張することができません。特許庁へ「実用新案技術評価書」を請求し、実用新案権が有効であると評価された後で、初めて権利を行使することができるのです。
なぜ技術評価書が必要になるのか?
前提として、実用新案制度では特許制度と異なり実質的な審査が行なわれません。審査は行われますが、着目されるのは出願書類が正しい形式で記載されているか、実用新案としての基準を書類上で満たしているか、といった形式的なポイントに留まっています。
そのためすでに実用新案登録されているアイデアと重複した内容でも、審査を通過して登録されてしまうケースもあるのです。つまり実用新案登録されるだけでは、実際に「新規性」「進歩性」などの要件を満たしていることが確認されていない状態です。
こうした前提があることから、他者の模倣を中止するには、自分のアイデアが権利を主張するに値するかを客観的に証明してくれるものが必要となります。それが「実用新案技術評価書」です。
技術評価書において自分の実用新案権が有効であることが認められれば、他者に技術評価書を提示して警告を行ない、模倣を中止させることができます。
しかしながら技術評価書において権利の有効性が認められなかった場合、その実用新案権は法的な効力を持たないため模倣を中止させることができなくなります。
権利の有効性が確立されていない状態で模倣行為などに対する警告を行ない、その後に権利が無効であることが証明された場合、損害賠償責任が発生するため慎重な対応が必要です。
実用新案は簡易な審査であるからこそ短期間で権利を保持できるメリットがありますが、その権利を主張する際には一筋縄ではいかないデメリットがあることを念頭においておきましょう。
4.無効審判を請求されたら?
無効審判とは、当該権利が無効であるとの第三者からの申し立てにより、当該権利を無効にさせることができる審判です。
3.で技術評価書について解説しましたが、この無効審判において登録要件を満たしていないとして権利が無効であると判断された場合には実用新案権は消滅、すなわち当該権利の有効性は消滅してしまいます。また、第三者が技術評価書を請求し、評価によって権利が無効であると判断されるケースもあります。
無効審判や技術評価書の評価結果に対して今後も実用新案権を保持したいと考える場合、審判請求人に対して答弁書の提出や請求の範囲の訂正をするなどの対応が必要となります。請求の範囲の訂正については5.で解説します。
5.明細書や請求の範囲などの「訂正」をするには?
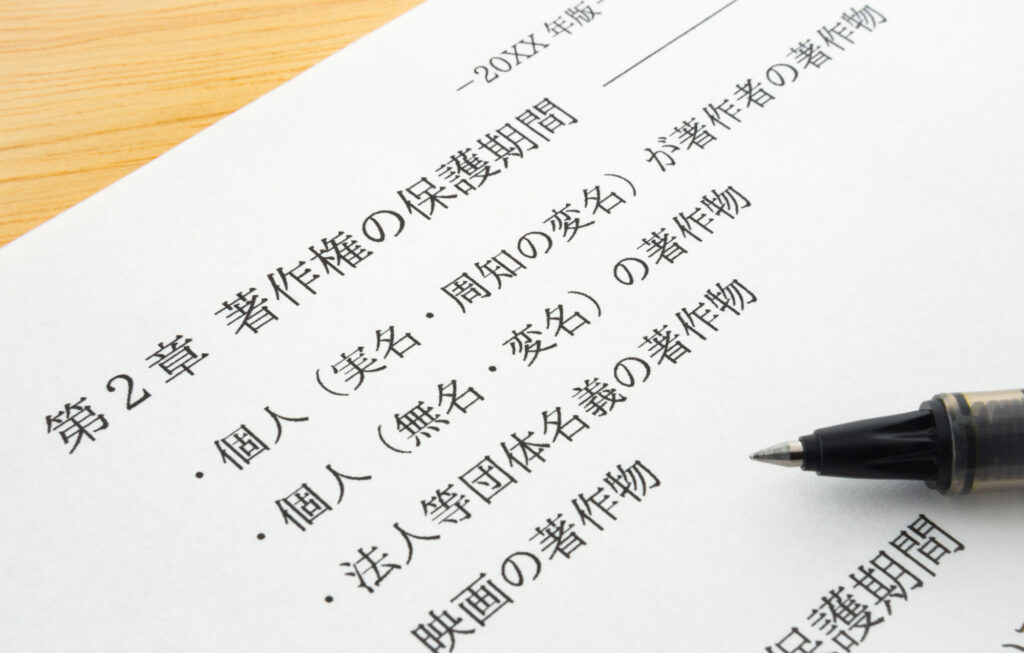
無効審判の請求をされた、あるいは技術評価書において権利が無効であるとの評価を受けた場合、出願書類を訂正することで権利の有効性が認められることがあります。
たとえば、Aさんの保持する登録された実用新案において「新規性」が欠けているために権利が無効であるとの評価を受けたとします。「新規性」欠如の原因は、当該実用新案権の実用新案登録請求の範囲にあたる内容が出願前に業界専門誌に記載されていたためでした。
しかしながら出願内容のすべてが重複していたわけではなく、請求項の一部に同一の内容が見られたという状況です。そこでAさんは当該実用新案権の権利範囲を狭めることで、出願日の段階では一般に公開されていないアイデアだけを自分の権利として主張することにしました。このように権利範囲を狭めたり、請求項の数を減らしたりすることを「減縮」と言います。
実用新案制度において、請求の範囲の減縮などを目的とする訂正は、一定の要件のもとで一度だけ可能であると定められています。一方で、請求の範囲の実質的な拡大や変更は禁じられています。
また、訂正に該当する行為は、前述の「実用新案登録請求の範囲の減縮、「誤記の訂正」および「明瞭でない記載の釈明」に限定されています。
6.登録された実用新案を特許出願に変更するには?
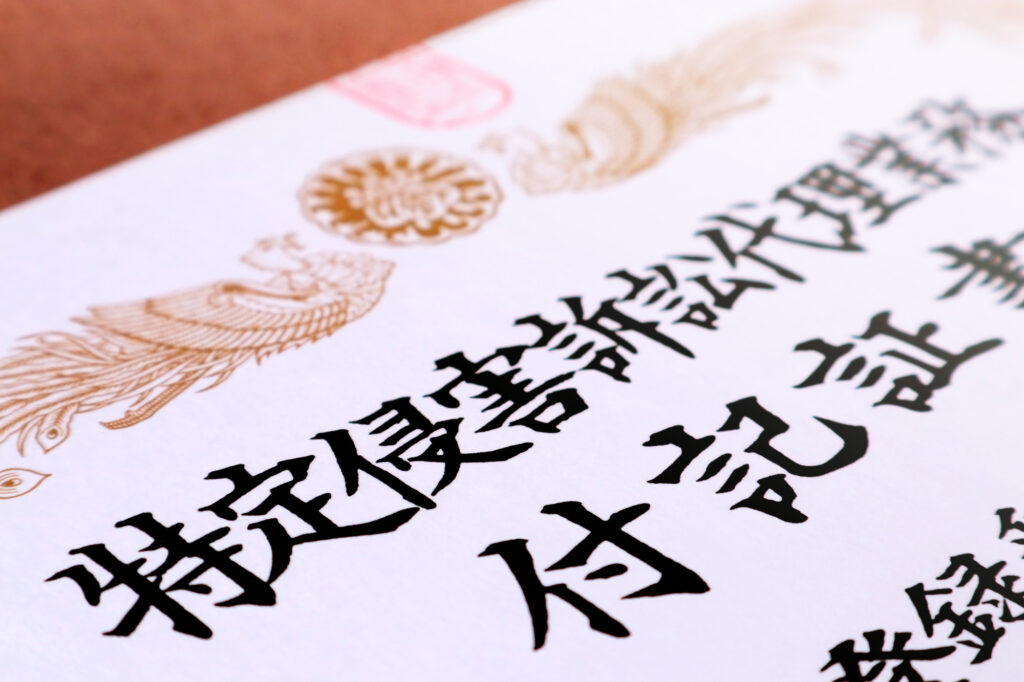
登録された実用新案は、一定の要件のもとでを特許出願に切り替えることができます。しかしながら、特許出願へと変更する際には実用新案権を放棄しなければならないため慎重な判断が必要となります。また、次の事項に一つでもあてはまる場合には特許出願へと変更することはできません。
- 実用新案の出願日から3年以上が経過している場合
- 出願人または権利者が実用新案技術評価書を請求した場合
- 第三者から実用新案技術評価書が請求された旨の通知を受け取った日から30日が経過した場合
- 無効審判を請求され、最初に指定された答弁書の提出期間が経過した場合
上記①の「3年」という期間は、特許制度における出願から出願審査請求までの猶予期間と類似しているといえます。特許制度では、出願をしても出願審査請求を行なわなければ実体審査が行なわれません。
それと同様に、実用新案制度においても出願日から3年間は特許出願に切り替えるか否かを検討する時間があると考えることができます。
また、登録された実用新案を特許出願に切り替えただけでは実体審査は行なわれません。通常の特許出願の手続きに準じ、所定期間内に出願審査請求を行なうことを忘れないようにしましょう。
7.まとめ
短期間で安価かつ簡易に権利を保持できる実用新案。一方で、権利の有効性が確実でなく、必ずしも権利を行使できるとは限らないという側面もあります。
しかしながら「実用新案登録されている」という事実において、他者からの模倣を抑止するという目的においては一定の効果が見込めるといえます。
メリットとデメリットをしっかりと理解し、ポイントを押さえて万全の状態で出願に臨みましょう。